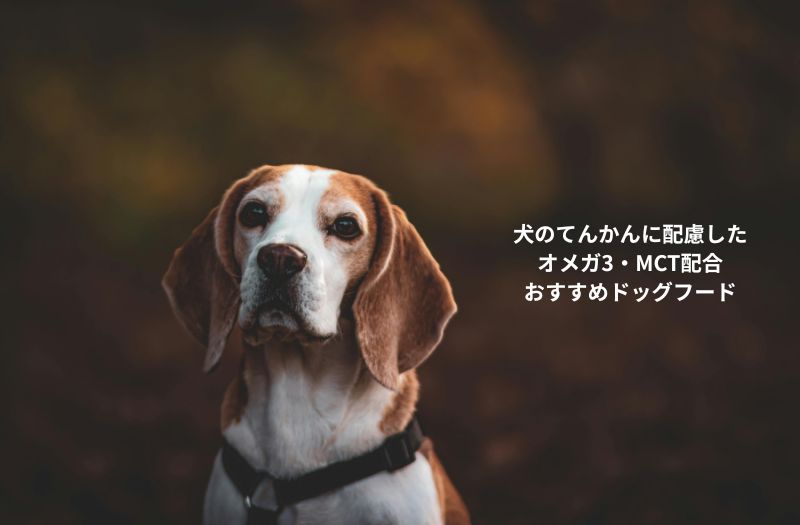犬の去勢・避妊手術を考えるとき、多くの飼い主さんが気になるのが「費用はいくらかかるのか」ではないでしょうか。病院や犬の大きさによって料金は変わるため、相場や助成金の有無を知っておくと安心できます。
この記事では、去勢・避妊手術にかかる費用の目安と、手術の流れや受けさせる時期の考え方、メリット・デメリット、術後の食事管理のポイントをまとめて解説します。愛犬にとってベストなタイミングを検討する際の参考にしてください。
小型犬で 15,000~35,000円台が一般的です。メスは開腹手術のため、オスより高くなる傾向があります。
■ オス(去勢手術)の費用目安
小型犬:15,000〜30,000円前後
中型犬:25,000〜40,000円前後
大型犬:35,000〜60,000円前後
→含まれることが多い項目
・麻酔代 ・手術料 ・術後の処置
※ 血液検査・エリザベスカラー・術後服は追加になることもあります。
■ メス(避妊手術)の費用目安
小型犬:25,000〜45,000円前後
中型犬:35,000〜55,000円前後
大型犬:45,000〜80,000円前後
→含まれることが多い項目
・麻酔代 ・開腹手術料 ・入院費(1泊のことも)
■ 費用が高くなりやすいケース
・体重が重い
・血液検査・レントゲンが必要
・発情期・子宮蓄膿症などリスクがある
・都市部の動物病院
・入院が必要な場合
犬の去勢・避妊手術とは?
去勢・避妊手術は、犬が繁殖できないようにするために行う代表的な外科処置です。
去勢手術(オス犬):精巣を摘出する手術。比較的短時間で終わることが多いです。
避妊手術(メス犬):卵巣または卵巣・子宮を摘出する手術。去勢よりも身体への負担がやや大きくなります。
どちらも全身麻酔で行われ、数時間の処置で終了するのが一般的です。
手術の流れ
血液検査やレントゲンで麻酔リスクを確認。年齢や健康状態によっては追加検査も行います。
全身麻酔下で摘出を実施。数時間で終了し、麻酔からの回復を確認します。
半日〜1日の入院で経過観察。病院によっては日帰りも可能です。
術後10日前後に抜糸。回復状態や生活上の注意を再度チェックします。
手術の時期
小型犬:生後6〜12か月頃
中型犬:生後8〜12か月頃
大型犬:12か月以降を推奨されることもあります
発情前に行うと病気予防効果が高いといわれていますが、犬種や体格、成長スピードに応じて判断することが大切です。
犬の去勢・避妊手術の費用の目安と助成制度
犬の去勢や避妊手術にかかる費用は、犬の体格や住んでいる地域、選ぶ動物病院によって大きく変わります。
先ほどの費用目安を踏まえたうえで、金額が変動しやすいポイントと、自己負担を減らせる助成制度の仕組みを押さえておくと、手術の日程や病院選びを進めやすくなります。
費用が変わりやすい理由
同じ去勢・避妊手術でも、次のような条件によって総額が上下します。
体格や体重(大型犬ほど高くなる)、日帰りか入院ありか、術前検査(血液検査・レントゲン)の有無、術後服やエリザベスカラーなどの追加グッズ、地域や動物病院ごとの料金設定などが重なると、同じ犬種でも見積もりに差が出ることがあります。
気になる場合は、事前に複数の病院でおおよその費用を確認しておくと安心です。
助成金・補助金の活用
多くの自治体では、犬の去勢・避妊手術に対して一頭あたり5,000〜20,000円前後の助成金や補助金が用意されています。ただし、申請できる期間が決まっていたり、頭数制限や指定動物病院の条件がある場合も少なくありません。
最新の受付状況は、市区町村のホームページや役所、動物愛護センターで必ず確認し、申請方法や締め切りをチェックしておきましょう。
去勢・避妊手術のメリットとデメリット
犬の去勢・避妊手術には多くのメリットがありますが、同時にデメリットやリスクも存在します。飼い主さんが冷静に判断できるよう、両面を整理して確認しておきましょう。
| ✅ メリット | 🔴 デメリット |
|---|---|
| 望まぬ妊娠を防げる | 手術費用がかかる |
| 発情期のストレスを軽減できる | 全身麻酔のリスクがある |
| 子宮蓄膿症や精巣腫瘍などの病気を予防 | 太りやすくなる犬もいる |
| 発情期特有の行動トラブルを減らせる | 数日は安静に過ごす必要がある |
去勢・避妊手術は、将来的な病気予防やストレスの軽減といった健康面の効果が大きいのが特徴です。特にメスでは子宮蓄膿症や乳腺腫瘍のリスクが下がり、オスでは前立腺肥大や精巣腫瘍の予防につながります。
一方で、費用負担や全身麻酔のリスクは無視できません。術後は安静が必要で、犬によっては体重が増えやすくなるため、フードの量や運動量の調整が求められます。
ホルモンの変化によって、性格や行動に少し変化が見られることもあります。「元気がない」「落ち着きがなくなった」などの違いを感じたときは、こちらの記事も参考になります。
➡ 避妊・去勢後に犬の性格が変わるのはなぜ?元気がない・腰振る理由と対策
手術をしない選択肢
犬の去勢・避妊手術は必ずしも受けさせなければならないものではありません。状況によっては手術を行わないという判断も考えられます。その場合にどんな場面があり、どんな工夫が必要かを整理してみましょう。
手術を見送ることがある場面
繁殖を希望している家庭や、犬が高齢で麻酔リスクが高い場合、持病を抱えていて体に大きな負担がかかると予想されるケースでは、無理に手術をしないという判断が選ばれることもあります。
その際は、定期的な健康診断や病気の早期発見を重視し、生活面での管理を丁寧に行うことが大切です。
見送る場合のリスク管理ポイント
手術をしない選択をした場合には、発情期に伴う行動や病気リスクを軽減する工夫が求められます。たとえば散歩のコースや時間を工夫して異性犬との接触を避ける、逸走防止を徹底する、マーキングやストレス行動に配慮するなどです。
家庭全体でルールを統一し、犬が安心できる環境を整えることで、健康面と生活面の両方を守ることができます。
飼い主さんの体験談
実際に去勢・避妊手術を受けさせた飼い主さんの声は、費用や準備を考えるうえで参考になります。ここでは編集要約した3つのエピソードをご紹介します。
助成金を利用して負担を軽減できたケース
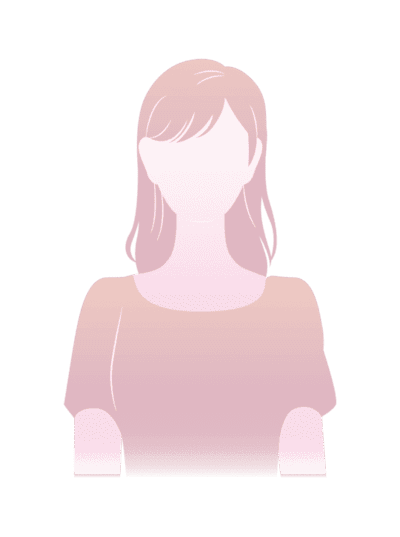
自治体から1万円の助成金が出て、自己負担が想定より少なく済みました。申請には期限があったため、早めに調べて申込みをしたのが正解でした。知らずに手続きを逃してしまうと、後から後悔することもあると思います。
大型犬の避妊手術で費用が高額になったケース

体格が大きい犬の避妊手術では、手術費用だけでなく麻酔や術後の薬代も加算され、合計で5万円を超えました。事前に病院ごとに見積もりを比較し、金額の違いを把握できたことで準備がしやすくなりました。
術前検査や薬代で追加費用がかかったケース

基本料金だけで考えていたのですが、術前の血液検査と術後の薬代で1万円近く追加されました。病院によっては見積もりがシンプルすぎて後から金額が増えることもあるので、内訳を細かく確認しておくことが大切だと感じました。
手術前に確認すべきチェックリスト(保存用)
去勢・避妊手術を検討するときは、費用や助成金の有無だけでなく、病院の方針や術後のケアまで含めて総合的に確認することが大切です。チェックリストを参考に準備を整えておきましょう。
見積もりと費用の内訳を確認する
手術費用は病院によって提示方法が異なり、基本料金だけを示しているケースもあります。実際には検査費用、麻酔代、薬代、抜糸後の再診料などが追加され、最終的な総額が想定より高くなることも少なくありません。
必ず項目ごとに内訳を確認し、総額で比較することが重要です。
助成金や保険適用を調べておく
自治体の助成金は申請期間や頭数制限があり、気づいたときには申請期限を過ぎていることもあります。また、ペット保険によっては去勢・避妊手術が補償対象外となる場合が多いため、加入中の保険内容を再確認しておくと安心です。
金銭的な支援の有無を早めに調べることが負担軽減につながります。
術後のケア体制と入院の要否を確認する
手術後にどの程度安静が必要か、入院するのか日帰りかは病院によって異なります。夜間や休日にトラブルが起きたときの連絡方法、緊急対応の体制があるかも大切な確認事項です。
さらに術後服やエリザベスカラーの準備が必要な場合もあるため、退院時に必要なケア用品の説明を事前に受けておくと慌てずに済みます。
手術前のチェックリスト
準備抜けを防ぐために、印刷して使える観点です。
□ 総額見積もり(手術料・検査・麻酔・薬・再診・抜糸を含むか)
□ 支払い方法(カード可/分割可)・キャンセル規定
□ 助成金の有無・申請〆切・必要書類
□ 術前検査の内容と追加費用の可能性
□ 麻酔リスクの説明と緊急対応体制(夜間対応の有無)
□ 当日の持ち物(ケージ、術後ウェアやカラーの手配)
□ 入院の要否と面会可否、連絡手段(電話・LINEなど)
□ 術後ケアの指示(投薬、運動制限、再診スケジュール)
□ ペット保険の補償対象かどうか
□ 予算の上限設定と、見積もりの病院間比較
こうしたチェックを事前に行えば、後悔のない選択につながります。
術後の体調管理には、食事面での配慮も欠かせません。去勢・避妊後のホルモン変化で太りやすくなる子も多いため、フード選びを見直しておくと安心です。
よくある質問|去勢・避妊手術の費用について
(タップで回答)
去勢と避妊ではどちらの方が費用が高いですか?
一般的に避妊手術の方が体への負担が大きく、摘出範囲も広いため費用は高くなる傾向があります。去勢は15,000〜30,000円前後ですが、避妊は25,000〜50,000円程度かかるケースが多いです。
(タップで回答)
手術費用は分割払いやクレジットカードで支払えますか?
多くの動物病院では現金払いが基本ですが、クレジットカードや分割払いに対応しているところもあります。高額になる場合は事前に支払い方法を確認し、無理のない形で準備しておくと安心です。
(タップで回答)
助成金は誰でも受けられるのでしょうか?
助成金は自治体によって条件が異なり、住民登録や犬の登録が済んでいること、頭数制限があることが多いです。早期に受付が終了する場合もあるため、役所や愛護センターに早めに問い合わせるのがおすすめです。
(タップで回答)
費用に含まれない追加料金にはどんなものがありますか?
術前の血液検査、麻酔、術後の薬、エリザベスカラーや術後服などが別料金になることがあります。病院によって含まれる範囲が違うため、内訳を必ず確認してから決めるようにしましょう。
(タップで回答)
ペット保険で去勢・避妊手術は補償されますか?
多くのペット保険では去勢・避妊手術は予防目的とされ、基本的に補償対象外です。ただし一部の保険やオプションでは補償がある場合もあるため、契約内容を確認してから判断すると安心です。
まとめ|費用と準備を知って納得の判断を
犬の去勢・避妊手術は、オスで15,000〜30,000円、メスで25,000〜50,000円程度が目安です。自治体の助成金を活用すれば負担を抑えることができ、費用面での不安も軽減できます。
メリットには病気予防や生活の安定がありますが、麻酔リスクや太りやすさなどのデメリットも理解しておく必要があります。必ずしも手術が正解というわけではなく、年齢や健康状態に応じて「行わない選択」も合理的です。
事前に見積もりを細かく確認し、助成制度やケア体制を調べておくことで、納得感のある判断ができるでしょう。術後は体重管理のためにフード内容の見直しも大切になるため、食事面での準備も忘れずに進めてください。

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。
ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。
成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。
愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami
愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。
参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。
本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。