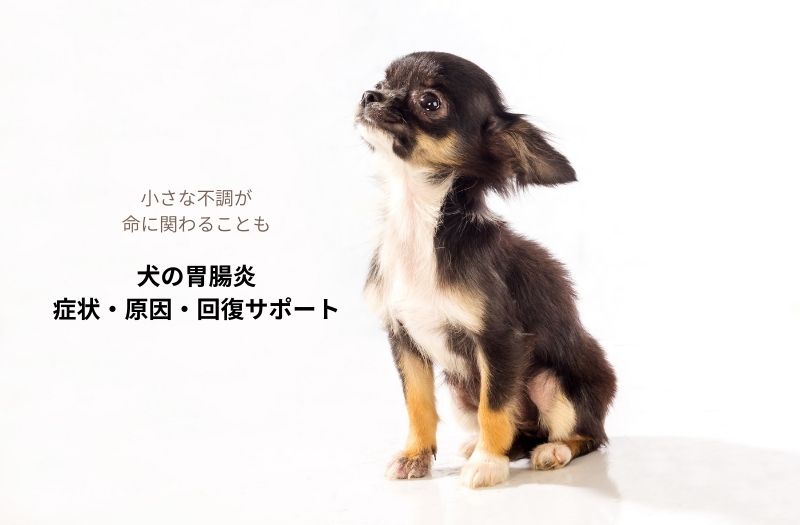犬の拡張型心筋症(DCM)は、心臓の力が弱まり、体に十分な血液を送れなくなる病気です。
特に大型犬に多く見られますが、小型犬でも起こることがあります。初めは「ちょっと疲れやすいかな」「咳をすることが増えたかな」といった小さな変化から始まるため、気づきにくいのが特徴です。
原因には遺伝や体質、栄養面の影響も関わるとされており、診断や治療を理解して早めに対応することが大切です。
本記事では、原因や症状、治療や栄養サポート、そして余命や最期のサポートについて、飼い主さんにわかりやすくまとめました。
拡張型心筋症(DCM)とは
犬の拡張型心筋症(DCM)は、心臓の筋肉が弱まり、体に十分な血液を送れなくなる病気です。心筋が薄くなり、ポンプ機能が落ちていくことで、全身に酸素や栄養が行き渡らなくなります。
進行すると呼吸の異常や疲れやすさなどが現れ、命に関わる深刻な状態へとつながることもあります。大型犬で多く見られますが、小型犬にも発症する可能性があります。
拡張型心筋症の原因と気をつけたい犬種
犬の拡張型心筋症(DCM)は、遺伝や栄養バランスの乱れなどが影響し、特定の犬種で特に発症しやすい病気です。原因とリスク犬種を理解することで、早期の気づきや予防的なケアにつながります。
遺伝や体質による発症リスク
拡張型心筋症は、遺伝的な素因や体質が大きく関係する病気です。特に大型犬は心臓に負担がかかりやすく、遺伝的に心筋が弱い個体は若いうちから症状が現れることがあります。
家系的に心臓病が多い場合はリスクが高いため、健康診断や定期的な心エコー検査で早期に異常を見つけることが大切です。
食べ物や栄養不足との関係性
タウリンやカルニチンといった栄養素は心筋の働きを支える重要な役割を果たします。これらが不足すると心臓の収縮力が低下し、DCMを発症する要因になると考えられています。
特に手作り食や偏った食事では栄養バランスが崩れやすく、知らず知らずのうちに不足してしまうこともあります。毎日の食事を見直し、栄養管理を意識することが予防の一歩となります。
発症リスクが高い犬種一覧
DCMはどの犬でも起こり得ますが、特に遺伝的に発症しやすい犬種が知られています。代表的なのはドーベルマン、グレート・デーン、ボクサー、アイリッシュ・ウルフハウンド、コッカースパニエルなどです。
これらの犬種は心臓に負担がかかりやすく、発症リスクが高いとされているため、飼い主さんは日常的に症状の有無を観察し、少しでも異変を感じたら早めに受診することが推奨されます。
遺伝的にDCMを発症しやすく、若いうちから症状が出ることも報告されています。
体が大きく心臓への負担が強いため、心筋が弱まりやすい犬種です。
不整脈や心臓病が多い犬種で、DCMも発症しやすい傾向があります。
大型犬特有のリスクが高く、心臓病全般に注意が必要です。
比較的小型ながらタウリン不足が関与するDCMが知られています。
拡張型心筋症の初期症状と診断の流れ
拡張型心筋症(DCM)は、進行するまで症状がわかりにくい病気です。早期に発見するには、飼い主さんが日常の変化を見逃さないことと、病院での検査が重要になります。
見逃しやすい初期症状のサイン
DCMの初期症状は軽度で目立たず、加齢や疲労と勘違いされやすいのが特徴です。咳や息切れ、運動を嫌がる、食欲や体重の低下などが代表的なサインです。
これらは一見よくある不調に見えますが、持続する場合は心臓病の可能性があるため、早めに動物病院での診察を受けることが望まれます。
動物病院で行われる診断方法
診断ではまず聴診で雑音や不整脈の有無を確認します。その後、胸部レントゲンで心臓の形や大きさを評価し、心エコー検査で心筋の収縮力や血流の状態を詳しく調べます。
さらに血液検査で心臓の負担を示すBNPなどの値を確認し、複数の検査結果を組み合わせて総合的に診断されます。こうした検査により病気の進行度や治療方針が決定されます。
治療法と手術の可能性
拡張型心筋症(DCM)は完治が難しい病気ですが、治療を続けることで進行を遅らせ、愛犬が快適に過ごせる時間を延ばすことができます。早めの診断と治療がとても重要になります。
薬物療法で期待できる効果
DCMでは、心臓の負担を和らげるために利尿薬や強心薬、血管を広げる薬などが処方されます。これらは血流を助け、息苦しさや疲れやすさを改善し、生活の質を保つことにつながります。
薬の種類や量は愛犬の体調や病気の進み具合に応じて調整されるため、獣医師の指導を受けながら継続して治療を行うことが欠かせません。
外科手術の選択肢と限界
外科的な手術はDCMではあまり一般的ではありませんが、重い不整脈を伴う場合にはペースメーカーの埋め込みが選択肢となることもあります。
ただし、体格や全身状態などによって適応が限られるため、すべての犬に行えるわけではありません。多くの場合は薬による治療が中心となり、愛犬に合った方法を獣医師と相談しながら選んでいくことが求められます。
完全に治る可能性はあるのか
現在のところ、DCMを完全に治す方法は見つかっていません。しかし、早期に発見して治療を始めれば、症状を抑えて愛犬が元気に過ごせる時間を延ばすことは可能です。
薬物療法や栄養管理を組み合わせることで、生活の質をできるだけ高く保てるようサポートできます。飼い主さんが病気を理解し、愛犬に寄り添いながら治療を続ける姿勢が何よりも求められます。
食事と栄養素でのサポート
拡張型心筋症(DCM)を抱える愛犬には、食事の工夫も欠かせません。特に心臓の働きを助ける栄養素を意識して与えることで、治療を支えるサポートとなります。
タウリンやカルニチンの重要性
タウリンやカルニチンは心筋の働きを助ける大切な栄養素で、不足すると心臓の収縮力が弱まり、病気の進行に関わる可能性があります。特定の犬種ではタウリン欠乏とDCMの関係が指摘されており、食事から十分に補うことが望まれます。
サプリメントや療法食で摂取することもあり、獣医師のアドバイスを受けながら取り入れることが安心です。
塩分や脂肪の制限と栄養管理
心臓に負担をかけないためには、塩分や脂肪の摂りすぎを避けることが大切です。塩分が多いと体に水分が溜まりやすく、心臓への負担が増してしまいます。
また、脂肪の多い食事は肥満を招き、循環器に悪影響を及ぼします。高品質なたんぱく質を中心に、必要な栄養素をバランスよく摂取できる食事を心がけることが、愛犬の健康を守る支えとなります。
心臓病と栄養の関係は研究が進んでおり、えんどう豆を多く含むフードとの関連についても議論されています。直接的な原因ではないものの、タウリン不足などと合わせて注意が必要です。
👉 犬にえんどう豆を与えるときの注意点
余命と最期のサポート
拡張型心筋症(DCM)は進行性の病気のため、残された時間をどう過ごすかも大切なテーマになります。余命の目安を知り、愛犬に寄り添ったサポートを考えていきましょう。
平均的な余命の目安について
DCMと診断された場合の余命は、病気の進行度や治療を始めるタイミングによって大きく変わります。平均すると数か月から数年と幅がありますが、早期に治療を開始した犬ではより長く穏やかに過ごせるケースもあります。
定期的に検査を行い、病気の状態を見極めながら治療を続けることが愛犬の寿命を延ばす支えになります。
最期の過ごし方と飼い主の支え
病気が進行すると呼吸のつらさや体の衰えが目立ってきます。その時期には、無理に延命を目指すよりも、愛犬が少しでも楽に過ごせるようサポートすることが大切です。
静かな環境を整え、安心できる場所で休めるようにしてあげると心が落ち着きます。飼い主さんの優しい声かけやスキンシップは、最期の時間を支える大きな力となります。
拡張型心筋症(DCM)に関するよくある質問
(タップで回答)
運動はさせても大丈夫ですか?
激しい運動は心臓に負担をかけるため避けた方が安心です。ただし、軽い散歩や緩やかな運動は気分転換になり、体力維持にもつながるので、愛犬の様子を見ながら無理のない範囲で続けましょう。
(タップで回答)
サプリメントは役立ちますか?
タウリンやカルニチンなどのサプリは、心臓の働きを助けるサポートになる場合があります。ただし効果には個体差があるため、期待しすぎず食事とのバランスを考えて取り入れることが大切です。
(タップで回答)
食欲が落ちてきた時はどうすればいいですか?
食欲が落ちるのは病気の進行や薬の影響による場合もあります。食事を柔らかくする、香りを強める、好きな食材を少量混ぜるなど工夫することで食べやすくなることがあります。
(タップで回答)
セカンドオピニオンを受けてもいいですか?
もちろん受けても問題ありません。心臓病は長期的に向き合う病気なので、信頼できる治療方針を見つけることがとても大切です。複数の意見を聞くことで不安が和らぎ、納得感を持って治療を進められることもあります。
拡張型心筋症(DCM)についてのまとめ
犬の拡張型心筋症(DCM)は、遺伝や栄養不足などが関わり、特定の犬種で発症しやすい心臓病です。初期症状は気づきにくいものが多く、咳や疲れやすさ、食欲の低下など小さなサインを見逃さないことが大切です。
診断には心エコーや血液検査などが用いられ、治療は薬物療法を中心に進められます。完治は難しいものの、栄養管理や生活環境の工夫で進行を遅らせ、愛犬が穏やかに過ごせる時間を延ばすことは可能です。
余命や最期についても正しい知識を持ち、無理のないサポートを続けることで、愛犬にとっても飼い主さんにとっても後悔の少ない時間を過ごすことにつながります。

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。
ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。
成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。
愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami
愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。
参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。
本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。