
「愛犬がトイレに行く回数が増えた」「おしっこをした後に痛そうにしている」 そんな様子を見て、動物病院で「膀胱炎」と診断された経験を持つ飼い主さんは少なくありません。
膀胱炎は、抗生物質などで治療すれば一度は良くなりますが、実は「非常に再発しやすい」のが特徴です。「薬で治ったと思ったのに、またすぐに繰り返してしまう……」と悩んでいませんか?
繰り返す膀胱炎のループから抜け出すために大切なのは、薬だけに頼るのではなく、「菌を溜めない体内環境」を毎日の食事で作ってあげることです。
この記事では、自宅でできる膀胱炎ケアの基本となる「水分補給」のテクニックや、膀胱の健康維持に役立つクランベリーなどの成分、そしてフード選びのポイントについて詳しく解説します。
膀胱炎ケアの基本は「水分補給」で菌を出すこと
犬の細菌性膀胱炎の多くは、尿道から侵入した細菌が膀胱の中で繁殖することで起こります。この細菌を体外へ追い出すための最もシンプルで強力な方法が、「おしっこの量と回数を増やすこと」です。
なぜ水が必要?おしっこの量と回数を増やすメリット
水分をあまり摂らず、おしっこを我慢している状態が続くと、膀胱内の尿は濃縮されていきます。濃いおしっこが長時間膀胱に留まることは、細菌にとって「繁殖しやすい最高の環境」を与えているようなものです。
水分をたっぷり摂って、薄いおしっこをジャブジャブと回数多く出すこと。これこそが、膀胱内を常に洗い流し(ウォッシュアウト)、細菌が定着するのを防ぐ一番の予防策になります。
ドライ?ウェット?食事から水分を摂るテクニック
「もっと水を飲んで」と言葉で伝えても、犬はなかなか飲んでくれません。そこで重要なのが、食事から自然に水分を摂取させる工夫です。
・ドライフードをふやかす: いつものカリカリフードをぬるま湯でふやかすだけで、食事と同時に水分補給ができます。香りが立って食いつきが良くなる効果もあります。
・ウェットフード(缶詰・パウチ)を活用する: ドライフードの水分量が約10%なのに対し、ウェットフードは約70〜80%が水分です。トッピングとして使うだけでも、摂取水量を大幅に増やせます。
・味付きスープやお肉の茹で汁: ただの水は飲まなくても、ササミの茹で汁や犬用スープなら喜んで飲む子は多いです。
膀胱の健康維持に注目したい「成分」と「食材」
水分補給で「菌を出す」ことに加え、膀胱の壁を丈夫に保ち、菌がくっつきにくい状態を作るための成分を食事に取り入れましょう。
クランベリー(プロアントシアニジン)の働きとは
人の膀胱炎ケアでも有名な「クランベリー」は、犬のサプリメントやケアフードにもよく使われています。注目すべきは、クランベリーに含まれる「プロアントシアニジン」というポリフェノールの一種です。
この成分には、膀胱の壁に細菌(特に大腸菌)が付着するのを防ぐ働き(抗付着作用)があると考えられており、菌の定着と増殖を抑えるサポートをしてくれます。
粘膜の健康を守るオメガ3脂肪酸とグルコサミン
膀胱の内側は粘膜で覆われています。繰り返す炎症でこの粘膜が傷つくと、さらに再発しやすくなってしまいます。
・オメガ3脂肪酸(EPA/DHA): 魚油などに含まれる良質なオイルです。抗炎症作用があり、膀胱の炎症を穏やかに鎮めるサポートが期待できます。
・グルコサミン・コンドロイチン: 関節ケアで有名ですが、実は「膀胱の保護層(グリコサミノグリカン層)」の修復を助ける働きもあります。
【目的別】膀胱炎に配慮したドッグフードの選び方
膀胱炎のケアを考える際、どのような基準でドッグフードを選べばよいのでしょうか。愛犬のタイプに合わせて選んでみましょう。
水分補給に特化した「ウェット・スープタイプ」
「とにかく水を飲まない」という子の場合は、ドライフードにこだわらず、主食をウェットフード(総合栄養食)に変えたり、食事のたびに水分補給ができるスープタイプを併用するのが近道です。
「下部尿路配慮」と書かれたウェットフードであれば、ミネラルバランスも調整されているため、より安心です。
クランベリーなどを配合した「下部尿路ケア」フード
ドライフードの中にも、膀胱の健康維持に配慮した製品があります。パッケージに「下部尿路の健康維持」や「pHコントロール」と書かれたものの中から、以下の成分が含まれているかをチェックしてみてください。
・クランベリー配合
・オメガ3脂肪酸配合
・抗酸化成分(ビタミンE・Cなど)
これらの成分が入ったフードを選ぶことで、毎日のごはんがそのままケアに繋がります。
食事だけでは難しい成分は「サプリ」も検討しよう
「今のフードはお腹の調子が良いから変えたくない」「クランベリー配合のフードを食べない」という場合は、無理にフードを変える必要はありません。
不足している成分だけをサプリメントで補うのが効率的です。粉末タイプやオイルタイプなら、いつものごはんにかけるだけで手軽にケアをプラスできます。
➡ 犬の泌尿器サプリ|膀胱炎・尿路結石のケア成分と選び方
※成分の詳しい働きや、おすすめのサプリメントの選び方はこちらで解説しています。
膀胱炎の再発防止・ケアにおすすめのフードと療法食
「水分を摂らせる」「成分で守る」というポイントを押さえた、編集部おすすめのフードをご紹介します。
【治療・食事療法に】獣医師が推奨する療法食
すでに膀胱炎や結石と診断されている場合に、尿のpHやミネラルバランスを管理するために開発されたフードです。

膀胱内の結晶や結石の管理に定評があり、多くの動物病院で推奨される定番の療法食です。

漢方やクランベリーを配合し、結石だけでなく膀胱炎の炎症ケアにも配慮された国産の療法食です。
【水分補給に】食いつきも抜群のスープ・ウェットフード
「とにかく水を飲まない」という子のために、食事と同時にたっぷりの水分を摂取できるタイプです。

フリーズドライ製法なので、ぬるま湯で戻すと香り高いスープ仕立てになります。おしっこで菌を流したい時に最適です。
【健康維持に】下部尿路をサポートするケアフード
日頃から尿トラブルが心配な子や、小型犬特有の悩みに配慮されたフードです。

尿が濃くなりがちな小型犬のために、飲水量を促し尿を薄めるよう工夫された健康維持食です。
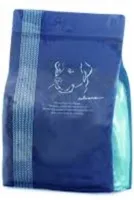
中型・大型犬でも満足できる容量で、クランベリーを配合。毎日のごはんから膀胱の健康をサポートできます。
これって膀胱炎?結石?症状の違いと注意点
「おしっこの回数が多い」「血尿が出た」という症状は、膀胱炎だけでなく「尿路結石」でも見られます。しかし、この2つは食事管理のポイントが少し異なります。
「頻尿・血尿」は共通のサイン。自己判断は禁物
細菌性の「膀胱炎」だと思って水分補給を頑張っていたら、実は大きな「結石」が尿道を塞いでいた、というケースもあります。
頻尿や血尿が見られたら、まずは動物病院で尿検査を受け、「菌がいるのか(膀胱炎)」それとも「結晶・石があるのか(結石)」をはっきりさせることが大切です。
結石(ストラバイト・シュウ酸)が見つかった場合の食事
もし病院の検査で「ストラバイト結晶」や「シュウ酸カルシウム結石」が見つかった場合は、水分の量だけでなく、ミネラル(リン・マグネシウム)の制限や、尿のpHコントロールが必要になります。
単なる膀胱炎ケアとは選ぶべきフードが変わってきますので、診断がついた場合は専用の食事療法を行いましょう。
➡ 犬の尿路結石(ストルバイト・シュウ酸)の食事療法ガイド
※尿路結石と診断された場合の食事療法については、こちらで詳しく解説しています。
犬の膀胱炎ケアでよくある質問
(タップで回答)
犬の膀胱炎はオスとメスで違いがありますか?
はい、一般的にはメス犬のほうが尿道が短く、外から細菌が入りやすいため膀胱炎になりやすい傾向があります。ただし、オス犬でも加齢に伴う前立腺の腫れや排尿障害によって膀胱炎を起こすことがあるため、どちらの性別でも注意は必要です。
(タップで回答)
膀胱炎になると夜間にトイレの回数が増えるのはなぜ?
膀胱に炎症が起きると、尿が少ししか溜まっていなくても排尿したいと感じるようになります。そのため、夜中でも何度もトイレに行きたがったり、落ち着かなくなったりする行動が見られることがあります。頻尿が続く場合は早めの受診が望ましいです。
(タップで回答)
膀胱炎になった犬は痛みを感じていますか?
膀胱炎にかかった犬は、多くの場合排尿時にチクチクとした痛みや違和感を感じています。症状が強い場合は、排尿の途中で鳴いたり、排尿後に陰部を過剰に舐めるような行動が見られることもあります。見た目に出ない場合もあるため、慎重な観察が大切です。
(タップで回答)
血尿が出たら受診の目安は?
目に見える血尿や頻尿・排尿時痛みが同時にある、ぐったりして水をよく飲む等が見られる場合は当日受診を。子犬・シニアは早めが安心です。
まとめ:清潔なトイレ環境と食事で再発を防ぐ
犬の膀胱炎は、一度なってしまうと癖になりやすい病気ですが、飼い主さんの日々のケアで再発のリスクを減らすことができます。
・水分をたっぷり摂らせて、菌を尿と一緒に追い出す
・トイレを我慢させない環境を作る
・クランベリーやオメガ3などの成分を食事に取り入れる
愛犬が痛い思いを繰り返さないよう、今日のごはんから「水分」と「成分」を意識してみましょう。
▼ あわせて読みたい
パグなどの一部の犬種は、遺伝的に尿路トラブルを起こしやすい傾向があります。日頃からおしっこの変化に注意してあげましょう。
➡ パグ向けドッグフード|太りやすい子・皮膚の悩みに配慮した選び方

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。
ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。
成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。
愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami
愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。
参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。
本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。




