
「えんどう豆入りのドッグフードは安全なの?」そんな疑問を持つ飼い主さんは少なくありません。えんどう豆は良質な植物性タンパク源として注目されていますが、アレルギーや心臓への影響を心配する声もあります。
この記事では、えんどう豆の栄養的な役割や、体質によって現れる症状、心臓病との関係などをわかりやすく解説します。
さらに、市販で手に入れやすいものを含めたおすすめフードもご紹介しますので、購入を検討している方にも役立つ内容になっています。
なお、ドッグフード全体の選び方や原材料・栄養バランスについて幅広く知りたい方は、愛犬ごはんノート|ドッグフード選びと健康サポートもぜひご覧ください。
犬にえんどう豆は与えても大丈夫?

えんどう豆は近年、多くのドッグフードに使われるようになってきました。植物性のタンパク源として優れており、グレインフリー(穀物不使用)フードの原材料としてもよく見かけます。
しかし、犬にえんどう豆を与えても本当に安全なのか、不安に感じる飼い主さんも多いと思います。えんどう豆の栄養的な利点と、与え方の注意点・気をつけたい症状をわかりやすく解説します。
原材料の見方に迷うときは、「ドッグフード選びの基準」もあわせて確認しておくと安心です。
ドッグフードに使われる理由と栄養価
えんどう豆は、タンパク質や食物繊維、ビタミン類が豊富で、低脂肪なのが特徴です。動物性原料の補完として使われることが多く、特にグレインフリーフードでは穀物の代わりに活躍します。
カロリーを抑えつつ栄養バランスを整えたいときにも役立つ原材料です。
与えすぎによる症状やリスク
えんどう豆は基本的に犬にとって安全とされていますが、過剰に摂取するとお腹にガスがたまりやすくなったり、下痢・軟便・消化不良を引き起こすことがあります。
また、体質によってはかゆみや赤みといった軽度のアレルギー反応が出ることもあるため、初めて与える場合は注意が必要です。
今もし何か症状が出ていてえんどう豆が疑われる場合は、動物病院でのアレルギー検査をおすすめします。
アレルギーやアトピーの原因になる?
えんどう豆は一部のドッグフードでは「アレルギーに配慮した原料」として使われていますが、すべての犬にとって無害とは限りません。体質によってはアレルゲンとなることもあるため、与える際には注意が必要です。ここでは、えんどう豆に対するアレルギーの症状や見極め方を解説します。
アレルギーを引き起こす可能性と症状
えんどう豆は穀物の代わりに使われることもある低アレルゲン食材ですが、すべての犬に安全とは限りません。
ごく一部の犬では、皮膚のかゆみや赤み、目の充血、耳をかく、くしゃみ、下痢や軟便、嘔吐といった症状が出ることがあります。こうした異変が現れたら、食事との関係を疑ってみましょう。
不安なときの見極め方と対処法
えんどう豆入りのフードを初めて与える場合は、まずはごく少量から始めてください。食後に皮膚やお腹の調子をよく観察し、異常があればすぐに中止しましょう。
症状が軽くても繰り返すようなら、アレルゲン検査を受けるのも有効です。不安な場合は獣医師に相談するのが安心です。
グリーンピースの安全性とえんどう豆との違い
大豆やひよこ豆、レンズ豆などは、えんどう豆と同じマメ科に属しますが、犬に与える際の注意点はそれぞれ異なります。大豆は高たんぱくで栄養価が高い一方、犬ではアレルゲンになりやすい食材です。
ひよこ豆やレンズ豆は食物繊維が豊富ですが消化に時間がかかるため、体質によってはお腹をこわす原因になることがあります。えんどう豆を含め、豆ごとに特徴を理解して与えることが大切です。
大豆や他の豆類との違い
大豆やひよこ豆、レンズ豆などの豆類は、えんどう豆よりもタンパク質が多く、犬によってはアレルギーを起こす可能性があります。これらはえんどう豆よりも消化に時間がかかり、体質によっては軟便やガスの原因になることがあります。
初めて与える場合は少量から試し、必ず茹でて柔らかくしておくと安心です。豆類共通の「食べ過ぎで消化負担になりやすい」点も踏まえ、トッピングとして少量にとどめることが健康維持につながります。
他の原材料も含めた成分全体の考え方や安全性を網羅した内容はこちらで詳しく解説しています。
➡ 犬のドッグフード成分と安全性|添加物・原材料・危険性
心臓病との関係は?DCMとの関連性
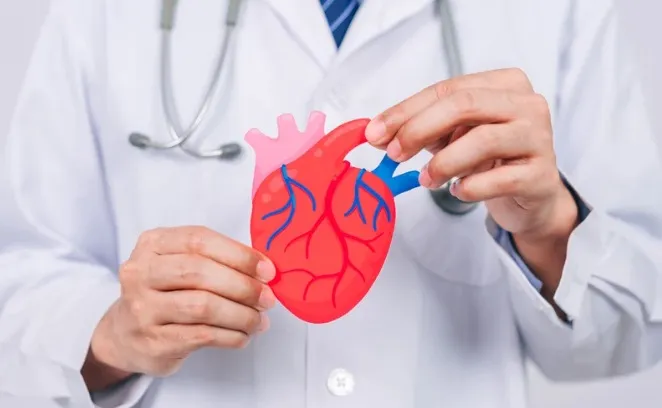
近年、えんどう豆を含む一部のドッグフードが「心臓病の原因になるのでは?」と話題になったことがあります。
とくにアメリカでは、拡張型心筋症(DCM)との関連性が指摘され、一部の飼い主さんの間で不安が広がりました。この章では、その背景と現在の見解を解説します。
えんどう豆の危険性と注意点
えんどう豆はドッグフードに広く使われていますが、犬によっては消化不良を起こしやすく、下痢や軟便、ガスがたまりやすくなることがあります。またアレルギー源となる場合もあり、かゆみや皮膚炎の原因になるケースも報告されています。
さらに2018年にはアメリカFDAが「えんどう豆やレンズ豆を多く含むグレインフリーフードと拡張型心筋症(DCM)の関連を示唆する報告」を発表しました。因果関係は未解明ですが、与える際は量や頻度に注意することが大切です。
DCMについては、原因や初期症状、治療の考え方まで全体像を知っておくと安心です。詳しくは、以下の記事で整理しています。
➡ 犬の拡張型心筋症(DCM)とは?原因・初期症状
現時点での獣医師・専門家の見解
現時点で、えんどう豆と心臓病の因果関係は明確に証明されていません。多くの専門家は「特定の成分が心臓病の主な原因であるとは言い切れない」としており、極端に避ける必要はないとされています。
ただし、心臓に不安のある犬には、獣医師と相談して食事を見直すことが大切です。
えんどう豆入りで安心なドッグフード2選
「えんどう豆は少し不安だけど、完全に避けるのは難しい…」という飼い主さんも多いでしょう。そこで、えんどう豆を使用していながらも、栄養バランスや品質に配慮された安心できるフードを厳選してご紹介します。
メディコート アレルゲンカット 魚&えんどう豆蛋白

アレルゲンになりやすい動物性たんぱく質を避け、魚とえんどう豆を主原料にした低アレルゲン設計のドッグフードです。合成着色料や保存料不使用で、皮膚やお腹がデリケートな犬にも安心。国産で品質管理もしっかりしており、コスパも良好です。
ドクターズケア アミノプロテクトケア えんどう豆

動物性原料を一切使わず、えんどう豆由来の加水分解たんぱくを主成分とした療法食です。
食物アレルギーの診断や管理を目的として設計されており、動物病院でも取り扱われています。獣医師の指導のもとで使用すれば、安心して与えられる製品です。
えんどう豆不使用のおすすめフード3選
「えんどう豆は避けたい」という飼い主さんに向けて、原材料にえんどう豆を含まない安心なドッグフードをご紹介します。アレルギーや心臓病が心配な場合の選択肢として、ぜひ参考にしてください。
【国産・完全無添加】このこのごはん
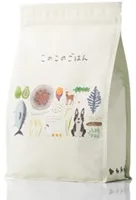
えんどう豆や豆類を使わず、低アレルゲンで構成された国産フード。アレルギーや消化の不安がある子にも配慮されており、「体にやさしいごはんをあげたい」と考える飼い主さんにぴったりです。
特徴
・えんどう豆不使用・グレインフリーではなく低アレルゲン穀物使用
・鶏ささみ、まぐろ、鹿肉など高たんぱくな国産素材を使用
・人工添加物・香料・保存料すべて無添加で安心
・涙やけ・アレルギー・食いつきの悩みに配慮した設計
【国産・小型犬専用設計】ミシュワン

えんどう豆や豆類を使わず、高たんぱく&やさしい雑穀をバランスよく配合した国産ドッグフード。小型犬の体に合わせて、皮膚・毛並み・腸内環境・食いつきの悩みに配慮されています。
人工添加物は不使用で、チキンや馬肉、かつおなどの動物性たんぱく源を中心に、栄養バランスとおいしさを両立したレシピです。
特徴
・えんどう豆・豆類不使用の低アレルゲンレシピ
・鶏肉・馬肉・鰹節など、食いつきと栄養価の高い動物性素材を使用
・小型犬専用設計で消化にも配慮された配合バランス
・雑穀(大麦・玄米・あわ・きびなど)を豊富に使用し、胃腸の調子を整えやすい
・人工添加物・香料・着色料・保存料すべて無添加
【市販】ZIWI エアドライ グラスフェッドビーフ
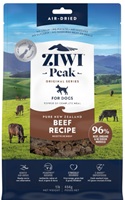
市販店でも取扱いがあるるZIWI(ジウィ)のエアドライドッグフードは、えんどう豆を使わないプレミアム系フードの有力候補です。
その主力製品「グラスフェッドビーフ」は、生肉・内臓・魚介類を96%配合し、豆類・穀類・芋類を使わない処方が特徴です。自然派ペットショップや大手ホームセンターのペットコーナーで見かけることもあり、店頭購入できる安心感があります。
ただし、製造ロットや地域によって取扱有無があるため、購入前に店頭で原材料表示を確認することをおすすめします。
えんどう豆入りフードに関するよくある質問
(タップで回答)
犬にえんどう豆を与えると危険ですか?
えんどう豆は少量であれば基本的に犬にとって危険ではありません。ただし消化不良や下痢、アレルギーを起こす犬もおり、与えすぎは健康への負担につながります。初めて与える際は少量から試し、体調に変化がないか観察しましょう。
(タップで回答)
犬にえんどう豆はどれくらいの量なら大丈夫?
えんどう豆は、体重5kgの犬で小さじ1杯ほどを目安に、まずは少量から与えると安心です。必ず茹でて柔らかくし、トッピング程度にとどめると消化の負担も少なく、安全に取り入れやすくなります。
(タップで回答)
えんどう豆と大豆の違いは何ですか?
えんどう豆は豆類の中でも比較的アレルギーが出にくいとされる一方、大豆はアレルゲンとなりやすく、避けたいと考える飼い主さんも多いです。
また、大豆は加工品に使われやすいのに対し、えんどう豆はドッグフードの主原料や炭水化物源として使用されることが一般的です。
(タップで回答)
レインフリーのフードには必ずえんどう豆が入っていますか?
グレインフリー=穀物不使用という設計上、その代わりに豆類(えんどう豆、ひよこ豆、レンズ豆など)が使われるケースが多いです。
ただし、必ずしも含まれているわけではなく、ジャガイモやタピオカなどを代用している製品もあります。原材料表示を確認しましょう。
(タップで回答)
えんどう豆が合わない犬にはどんなフードを選べばいい?
えんどう豆で下痢や皮膚の不調が出た場合は、豆類全般を避けたシンプルな原材料のフードに切り替えると安心です。動物性たんぱくを中心とし、炭水化物源にタピオカやさつまいもを使ったフードがおすすめです。アレルゲン対応フードも選択肢の一つです。
切り替えに不安がある場合は、「ドッグフードの切り替え方」を参考にしてください。
安心してえんどう豆と付き合うために
えんどう豆は良質なたんぱく源や食物繊維を含む栄養価の高い食材で、多くのドッグフードに使われています。ただし、体質によっては消化不良やアレルギー反応が出ることもあるため、慎重に様子を見ながら与えることが大切です。
拡張型心筋症との関連が話題になったこともありますが、現時点で因果関係は証明されていません。極端に避ける必要はありませんが、フードの原材料を確認し、心配な場合は獣医師に相談しましょう。
今回ご紹介したような、えんどう豆を上手に取り入れた安心できるフードを選ぶことで、健康的な食生活に役立てることができます。

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。
ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。
成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。
愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami
愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。
参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。
本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。




