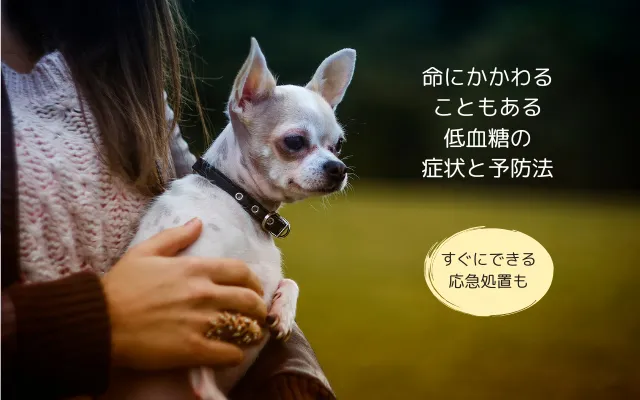
犬の低血糖は、小型犬や子犬に多く見られる病気で、放置すると命に関わる危険もある深刻な状態です。元気がなくなる、ふらつく、震えるなど、一見「ちょっとした体調不良」に見えることもあるため、早期の気づきが非常に重要です。
この記事では、低血糖の原因や症状、応急処置の方法、予防のための生活習慣までをわかりやすく解説します。もしものときに落ち着いて対応できるよう、日ごろから正しい知識を身につけておきましょう。
犬の低血糖とは?命に関わる病気
犬の低血糖とは、血液中のグルコース(ブドウ糖)濃度が異常に低下した状態を指します。ブドウ糖は犬の身体、とくに脳の働きにとって欠かせないエネルギー源のため、不足すると全身の機能に影響を及ぼします。
血糖が不足すると、エネルギーが行き渡らなくなり、ふらつき・震え・意識の混濁などが起こります。脳の働きに支障が出るため、小さな変化でも早めに気づくことが重要です。
さらに、子犬や体の小さい犬種では、エネルギーの蓄えが少ないため、急激に血糖値が下がることがあります。症状が出てからでは手遅れになることもあるため、普段の様子との違いを見逃さないことが大切です。
子犬や小型犬がなりやすい理由
子犬や小型犬は、成犬や大型犬に比べて低血糖を起こしやすい体質を持っています。これは、彼らの身体の仕組みや発育段階が関係しています。
食事間隔が空くと血糖値が下がりやすい
子犬や体の小さな犬は、体内にためておけるエネルギーの量が少ないため、食事の間隔が長くなると急激に血糖値が低下しやすくなります。
とくに朝食を抜いた場合や、夜間に長時間食事がとれなかったときに起こりやすく、日常的に食事のタイミングに注意が必要です。
成長期や体調不良時は要注意
子犬は内臓の働きが未発達で、血糖値を一定に保つ力がまだ十分ではありません。さらに、環境の変化やストレス、体調不良、ワクチン接種後の一時的な食欲不振なども、低血糖の引き金になります。こうした時期は特に注意深く観察しましょう。
小型犬や子犬は低血糖を起こしやすいため、体質や犬種に合ったフード選びも大切です。犬種別ドッグフード一覧で愛犬にぴったりの食事を探してみてください。
見逃さないで!低血糖の主な症状
低血糖は、初期段階では飼い主が気づきにくい軽い症状から始まります。しかし、放置すると急速に悪化し、命に関わる深刻な状態に進行することもあります。日常のちょっとした変化を見逃さず、早期発見につなげることが重要です。
元気がない・ふらつく・ぼんやりしている
血糖値が低下すると、体のエネルギーが不足し、犬は元気がなくなって動かなくなったり、足元がおぼつかなくなることがあります。
ふらつきながら歩く、急に寝そべる、呼びかけても反応が鈍い、目が虚ろになるなどの様子が見られたら、低血糖の可能性を疑いましょう。
震えや痙攣、意識の混濁が見られる
低血糖がさらに進行すると、震えや痙攣といった神経症状が現れ、次第に意識が薄れていきます。
そのまま放置すると昏睡や命の危険もあるため、すぐにブドウ糖の補給や動物病院での対応が必要です。特に普段と様子が違うときは早めの判断が重要です。
なお、発作のようなけいれんや意識消失が見られた場合は、低血糖以外に「てんかん」の可能性もあります。迷ったときは、以下の記事もあわせて参考にしてください。
➡ 犬のてんかん|症状・原因・治療法・食事の工夫
➡ てんかんに配慮したドッグフードの選び方(栄養素とおすすめ)
すぐできる応急処置と受診目安
低血糖は進行が早いため、気づいた時点で素早く対処することが重要です。応急処置で一時的に回復することもありますが、根本的な原因が改善されなければ再発の可能性も高くなります。
砂糖水やはちみつで素早くブドウ糖を補給
意識があり、舐めることができる状態であれば、砂糖水やはちみつ、ブドウ糖ジェルなどを口の中に塗って血糖を補うと、比較的短時間で回復することがあります。
無理に飲ませるのは危険なので、舌や歯茎に少しずつ塗るようにしましょう。回復後も油断せず、体調をよく観察してください。
意識障害やけいれんがあればすぐに受診を
震えやふらつきが強い、意識がはっきりしない、けいれんを起こしているなどの状態が見られる場合は、応急処置よりも早急な通院が最優先です。
無理に動かさず、体温が下がらないように保温しながら動物病院へ連れて行きましょう。到着時に症状を伝えるとスムーズです。
低血糖を予防する生活習慣と食事の工夫
低血糖は、毎日の食事のタイミングや運動量を見直すことで予防可能な病気です。特に子犬や小型犬では注意が必要です。
食事の間隔を空けすぎない工夫を
子犬や小型犬の場合、1日に必要なエネルギーを一度に摂るのが難しいため、食事を数回に分けて与えることが効果的です。
早朝や夜中に低血糖を起こしやすい犬には、寝る前に少量のおやつを与えるのも良い方法です。空腹の時間をできるだけ短くする意識が予防につながります。
他の体調不良と食事の関係については、症状別の食事解説ページで紹介しています。
👉犬がかかりやすい病気とごはんの工夫 >>
激しい運動後は栄養補給を忘れずに
運動によって多くのエネルギーが消費されると、血糖値が急激に下がることがあります。
お散歩や遊んだあとの水分補給と一緒に、消化のよい軽食を与えると安心です。また、疲れやすさや興奮が強い日は無理に運動を続けず、体調に合わせて調整しましょう。
低血糖予防に役立つ食材とは?
低血糖を防ぐには、エネルギー源となる食材を適度に取り入れることが重要です。以下のような食材は、血糖値の急激な変動を抑えつつ、体への負担も少ないためおすすめです。
ゆるやかに血糖値を上げる低GI食材で、ビタミンCや食物繊維も豊富です。消化もよく、朝食やおやつ代わりに向いています。
高たんぱく・低脂肪で、体を支えるエネルギー源になります。茹でて細かくしてごはんに混ぜると、食いつきもアップ。
アミノ酸バランスの良い完全栄養食のひとつ。ビタミンB群や脂質も含み、適量なら日々の栄養補助になります。加熱して与えましょう。
胃腸にやさしく、消化吸収も良好。たんぱく質源として低血糖時の体力維持にも役立ちます。
炭水化物と一緒に、ビタミンEやカリウムも摂れる食材。甘みがあるので食欲が落ちたときにも◎。
すぐにエネルギーになる炭水化物で、食間の間隔が空くときに少量与えるのも効果的。ただし与えすぎには注意しましょう。
これらの食材は、普段の食事にトッピングするだけでも血糖維持に役立ちます。不安がある場合は、獣医師と相談のうえで取り入れると安心です。
低血糖が心配な子には、栄養バランスや食事の間隔に配慮されたドッグフードを選ぶのもおすすめです。
👉朝ごはんを食べない犬に|低血糖・胃液嘔吐予防ができるおすすめフード4選 >>
避けたい食材とその理由
急激に血糖値を上下させるような食品や、犬の体にとって有害な成分を含む食材は避ける必要があります。
犬にとって中毒を引き起こす代表的な成分です。少量でも重篤な低血糖やけいれんを引き起こす恐れがあり、命に関わる危険があります。
急激に血糖値を上げた後に、反動で急降下しやすく、結果的に低血糖を引き起こす原因になります。人間用のお菓子は避けましょう。
脂肪の多い食事は消化に時間がかかり、胃腸に負担をかけます。特に空腹時に与えると、エネルギーとして使われるまでに時間がかかり、血糖が下がりやすくなることもあります。
保存料や香料などが多く含まれる人間用の加工食品は、犬の血糖調整に悪影響を与える可能性があり、体調を崩す原因にもなります。
愛犬には、犬専用に設計されたフードや、できるだけシンプルな素材を使ったごはんを選ぶことが基本です。体にやさしく、安定したエネルギー供給ができる食事が、低血糖の予防にもつながります。
手作りごはんの注意点
低血糖対策のために手作りごはんを与える場合は、栄養バランスに特に注意が必要です。炭水化物・たんぱく質・脂質をバランスよく取り入れ、糖分や塩分を加えすぎないようにしましょう。
また、必要な栄養素が不足すると逆に体調を崩すことがあるため、継続する場合は獣医師に相談するのが安心です。
時間帯別の食事で低血糖を予防しよう
朝は寝ている間に血糖が下がっているため、炭水化物とたんぱく質を組み合わせた朝食が大切です。ごはんと鶏むね肉、さつまいもなどの消化しやすい食材を少量ずつ与えると安心です。
夜は食間が長くなりがちなので、軽くふやかしたドッグフードや少量のおじやを寝る前に与えるのもおすすめ。食事回数を分けることで血糖の安定につながり、低血糖のリスクを抑えられます。
低血糖についてのよくある質問
低血糖に関して不安や疑問を抱く飼い主の方は多いです。ここでは、特によくある2つの質問にわかりやすくお答えします。
(タップで回答)
子犬が震えているのは低血糖ですか?
子犬が震える原因は複数ありますが、空腹時や活発に動いたあとで震えている場合、低血糖の可能性があります。
特にぐったりしていたり、目がうつろだったりする場合は注意が必要です。水や食べ物を与えて様子を見ながら、改善しない場合は早めに動物病院を受診しましょう。
(タップで回答)
低血糖の応急処置は家でもできますか?
意識があり、物を舐められる状態であれば、自宅でも応急処置は可能です。砂糖水やはちみつ、ブドウ糖ジェルなどを歯茎や舌に少しずつ塗ることで、血糖値の回復を促せます。
ただし、意識がない・けいれんがある場合は、応急処置よりも速やかに通院することが大切です。
愛犬の変化に早く気づくために
犬の低血糖は、小さな体の変化が命に関わる重大なサインとなることもある病気です。特に子犬や小型犬を飼っている方は、ふらつき・震え・元気がないなどの症状を見逃さないよう注意が必要です。
万が一のときに慌てないよう、日ごろから食事の管理や生活リズムの見直しを行い、低血糖のリスクを減らすことが大切です。応急処置や受診の判断ができるよう知識を備えておけば、もしものときも落ち着いて行動できます。
大切なのは、普段の様子をよく観察し、「いつもと違う」にすぐ気づくこと。愛犬の命を守るために、今日からできることを始めていきましょう。

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。
ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。
成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。
愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami
愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。
参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。
本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。




