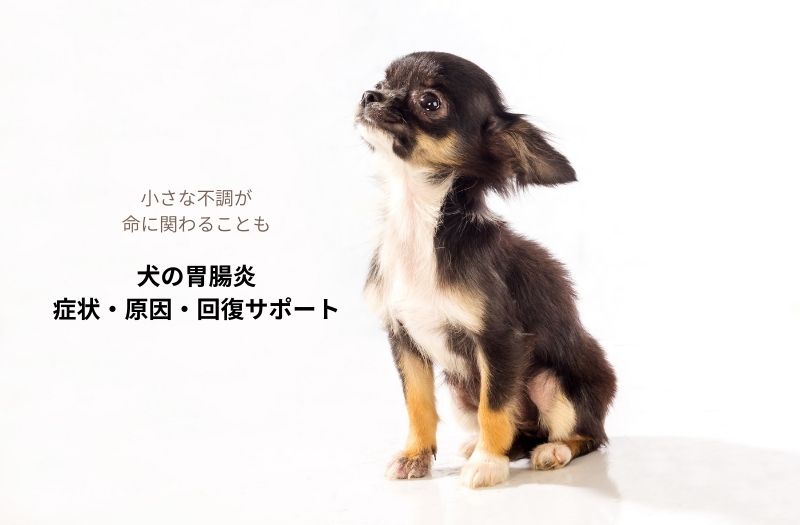レッグ・ペルテス病は、小型犬に多く見られる病気で、後ろ脚のびっこや痛みの原因になります。早めの受診が回復への第一歩です。進行の程度によって、安静や痛み止めで様子を見る場合もあれば、外科手術(FHOなど)を行うこともあります。
治療費は検査・手術・入院・通院の内容で異なり、おおよそ数十万円ほどかかることも。地域や病院によって差があるため、見積もりを確認しておくと安心です。
この記事では、初期サインから治療の流れ、費用やリハビリの目安までをわかりやすくまとめています。
レッグ・ペルテス病とはどんな病気?
レッグ・ペルテス病は、成長期の小型犬に多く見られる股関節の病気で、放っておくと痛みや歩きづらさが強くなってしまいます。まずは病気の全体像を知ることが、治療の方針を決める第一歩です。
理解が深まるほど、これからのケアにも落ち着いて向き合えます。
大腿骨頭壊死症の正式名称と仕組み
レッグ・ペルテス病の正式名称は「大腿骨頭壊死症」で、大腿骨の先端(骨頭)への血流が不足し、骨が壊死して変形する病気です。
骨頭が潰れると股関節に炎症や痛みが生じ、歩行に異常が出ます。病気は片足に起こることが多く、早期の診断と治療が必要です。
トイプードルなど小型犬に多い理由とは?
レッグ・ペルテス病はトイプードル、ミニチュア・ピンシャー、ヨークシャーテリアなどの超小型犬に多く見られます。
遺伝的な体質や骨の発育が関係しているとされ、特に成長期(生後5〜12か月)のオス犬に多く発症します。股関節への負担がかかりやすい体型も要因のひとつと考えられています。
成長期に骨の成長と血流バランスが崩れやすく、遺伝的に大腿骨頭の壊死を起こすリスクが高いとされています。活発でも骨が細く、ジャンプなどの衝撃に注意が必要です。
体は小さいのに運動量が多く、関節への負担がかかりやすい犬種です。骨が華奢で、後ろ足の血流障害が起こりやすいため、若齢期から注意が求められます。
遺伝的にレッグ・ペルテス病の発症例が多く報告されており、典型的な好発犬種です。小柄で筋肉量が少なく、関節の安定性が低いため歩行異常が出やすい傾向があります。
骨が細く関節が小さいため、少しの衝撃でも股関節に負担がかかります。特に成長期の栄養バランスが悪いと、骨形成不全を起こしてペルテス病を誘発する可能性があります。
運動好きでジャンプや走行が多いため、若年期に関節への負担が集中しやすい犬種です。筋肉は発達していますが、骨格の成長期に過度な運動をするとリスクが高まります。
遺伝的素因に加え、筋肉質で活発な動きが股関節を酷使しやすいタイプです。特に成長期の段差の上り下りや高い運動量が、発症の引き金になることがあります。
犬種により傾向はありますが、個体差が大きく不確かである点にもご留意ください。歩き方の違和感が数日続くときは早めの相談が安心です。
症状や気づきやすいサイン
レッグ・ペルテス病では、「スキップのような歩き方」や「片足を浮かせて歩く」といった小さな変化から始まることが多いです。痛みを我慢してしまう子もいるため、日々の仕草や抱き上げたときの反応を観察しましょう。
早めに気づけるほど、回復までの道筋が立てやすくなります。
歩き方の異常や足の痛み
レッグ・ペルテス病の初期症状として最も多いのは、片足をかばうような歩き方やスキップのような動きです。足を地面につけたがらなかったり、急にびっこを引いたりする様子が見られることもあります。
痛みが強くなると、触れられるのを嫌がるようになったり、安静を好むようになることもあるため注意が必要です。
進行するとどうなる?後遺症の可能性も
症状が進行すると大腿骨頭の変形が進み、股関節の動きに大きな制限が生じます。歩行困難になるだけでなく、骨の異常な形状によって関節炎を引き起こし、慢性的な痛みや後遺症が残るケースもあります。
後遺症を防ぐためには、できるだけ早い段階での治療と、その後の適切なリハビリが欠かせません。
原因と発症のメカニズム
レッグ・ペルテス病(大腿骨頭壊死症)は、血流の滞りや成長期の骨の変化が重なって起きると考えられています。はっきりした原因が分からないこともありますが、生活環境を整えることで悪化を防げる場合もあります。
できることから少しずつ整えていきましょう。
先天性や遺伝の関与はある?
この病気は特定の犬種に多く見られることから、先天的な体質や遺伝的素因が関係していると考えられています。特にトイプードルやミニチュア・ピンシャーなどでは、発症リスクが高いことが知られています。
両親犬の病歴を確認し、繁殖時に注意が払われているブリーダーから迎えることが、予防の一助になることもあります。
発症しやすい年齢や環境要因
レッグ・ペルテス病は、生後5〜12か月頃の成長期の犬に多く見られる病気です。骨の発育が活発な時期に、大腿骨頭への血流が何らかの理由で阻害されることが原因とされています。
また、過度な運動や滑りやすい床などの生活環境も、発症を悪化させる可能性があるため注意が必要です。
治療法と手術の流れ・費用の目安
レッグ・ペルテス病の治療は、痛みの強さや生活への影響を見ながら、安静中心の保存療法か手術を選びます。どちらも「痛みをやわらげ、歩ける状態に戻す」ことが目的です。主治医と相談し、愛犬に合う方法を一緒に考えていきましょう。
手術の方法と成功率・費用目安
代表的な手術方法は「大腿骨頭切除術」で、壊死した骨頭を取り除き、股関節の痛みを軽減させます。犬の体重や体格にもよりますが、小型犬ではこの手術によって日常生活に支障のない程度まで回復することが多いです。
費用は動物病院や地域によって差がありますが、数十万円規模になることが多いです。
| 項目 | 目安費用 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 初診・画像検査 | 1〜5万円前後 | レントゲンやCTなどを行う場合 |
| 手術(FHOの目安) | 15〜40万円前後 | 体格や入院日数で増減 |
| 術後通院・リハビリ | 数千〜数万円/回 × 回数 | 内容・頻度で変動 |
手術を選ぶ場合、術式や入院日数で費用は変動します。一般には検査+手術+通院で数十万円規模になることが多いため、見積もりを確認しておくと安心です。
金額は病院規模や体格、合併症で大きく変わるため不確かである点にご留意ください。見積もりの提示を受けて検討するのがおすすめです。
手術後のリハビリと経過観察
手術後は数週間から数ヶ月にわたるリハビリが必要となります。軽い散歩から始め、徐々に筋力を回復させていくことが重要です。
関節の柔軟性を保ち、再発や別の脚への負担を防ぐためにも、獣医師の指導に基づいたケアを行いましょう。定期的な診察で経過を確認することも大切です。
手術しない選択はできるのか?
症状が非常に軽い場合や、年齢・持病の関係で麻酔リスクが高い場合などには、手術をせずに保存療法を選ぶこともあります。安静や鎮痛剤の投与、体重管理などで痛みをコントロールしながら経過を観察します。
ただし、根本的な治療にはならないため、多くの場合は改善が見込めず、長期的に不自由が残る可能性もある点に留意が必要です。
再発や後遺症のリスクと予防法
手術で良くなっても、レッグ・ペルテス病は術後ケアがとても大切です。体重管理やリハビリ、滑りやすい床や段差の見直しなど、日常の小さな工夫が将来の歩きやすさを守ります。焦らずコツコツ続けていきましょう。
再発の可能性と術後の注意点
基本的にレッグ・ペルテス病は同じ脚で再発することはありませんが、術後にバランスを崩してもう片方の脚に負担がかかるケースはあります。
リハビリを適切に行い、体重をしっかり管理することで、関節への余計な負担を減らすことができます。滑りやすい床や段差を避けるといった環境の見直しも、再発防止には欠かせません。
リハビリ・散歩・生活環境の工夫
術後は急な運動を避け、散歩も段階的に時間を延ばしていくことが大切です。また、柔らかすぎるベッドやツルツルした床は関節への負担となるため、滑り止めマットや適度な硬さの寝具を選びましょう。
似たような症状を持つ膝蓋骨脱臼(パテラ)との混同も多く、症状や原因の違いを正しく理解することが大切です。
→ 膝蓋骨脱臼(パテラ)の症状と治療法について詳しくはこちら
食事と体重管理のポイント
レッグ・ペルテス病の回復を支えるには、関節への負担を増やさない体重コントロールが鍵です。高品質なたんぱく質や関節サポート成分を意識しつつ、カロリー過多を防ぐ与え方を習慣に。小さな見直しが、からだの軽さにつながります。
関節の負担を減らす栄養とは?
関節の健康維持には、グルコサミンやコンドロイチン、オメガ3脂肪酸などの栄養素が有効です。これらは関節の炎症を抑え、滑らかな動きをサポートする効果が期待されます。
また、ビタミンDやカルシウムも骨の強化に役立つため、バランスの良い食事で補うことが大切です。
高たんぱく・低脂肪フードの選び方
術後のリハビリや筋力維持のためには、質の良いたんぱく質を多く含んだフードがおすすめです。脂肪分を抑えることで、肥満による関節への負担を軽減できます。
市販の高たんぱく・低脂肪フードを選ぶ際は、原材料の肉の比率や不要な添加物の有無をチェックし、安心できるブランドを選びましょう。
食事や体重管理は、レッグ・ペルテス病の再発予防や関節の保護に欠かせません。関節の健康を支える成分を含むフードを選ぶことで、日常の動きをやさしくサポートできます。
➡ 犬の関節にいいドッグフード3選
レッグ・ペルテス病に関するよくある質問
(タップで回答)
犬がレッグ・ペルテスになる確率は?
発症率の正確な数値は犬種構成や調査方法で差があり、全体としては「まれ」とされています。とくに小型犬(トイプードル、ポメラニアン、ヨークシャーテリア、チワワ等)の若齢で相対的にリスクが高いと報告があります。跛行や後肢の痛みがあれば早めに受診しましょう。
(タップで回答)
レッグ・ペルテス病は他の関節疾患とどう見分けますか?
膝蓋骨脱臼や股関節形成不全と症状が似ており、歩き方だけでは判断が難しい場合があります。レントゲンやCT検査によって骨頭の壊死や変形を確認することで、正確な診断が可能になります。
(タップで回答)
レッグ・ペルテス病は放置するとどうなりますか?
放置すれば股関節の変形が進行し、強い痛みや歩行困難につながります。最終的には慢性的な関節炎を引き起こし、日常生活に大きな支障が出るため、放置せず早期の対応が必要です。
(タップで回答)
どんな床材がレッグ・ペルテス病の犬に適していますか?
フローリングのような滑りやすい床は避け、滑り止め効果のあるマットやカーペットを敷くのが望ましいです。関節への負担を軽減し、術後のリハビリや転倒防止にもつながります。
回復に向けた大切なポイント
小さな違和感に気づけたことが第一歩。焦らず、痛みを減らし歩きやすさを取り戻す準備から始めましょう。
レッグ・ペルテス病は、早期発見と適切な選択で、回復の道筋が見えやすくなる病気です。方針は保存療法か手術かに分かれますが、目的はどちらも「痛みをやわらげ、動ける体に戻す」こと。
治療後は、滑り対策や段差回避などの環境づくり、体重管理、主治医の指示に沿ったリハビリをコツコツ続けることが力になります。費用は病院や体格で差が出やすいため、検査・手術・通院を段階ごとに見積もり確認しておくと安心です。
歩き方に変化を感じたら、無理をさせず早めに相談を。できることを一つずつ積み重ねれば、明日の“歩きやすさ”はきっと近づきます

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。
ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。
成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。
愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami
愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。
参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。
本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。