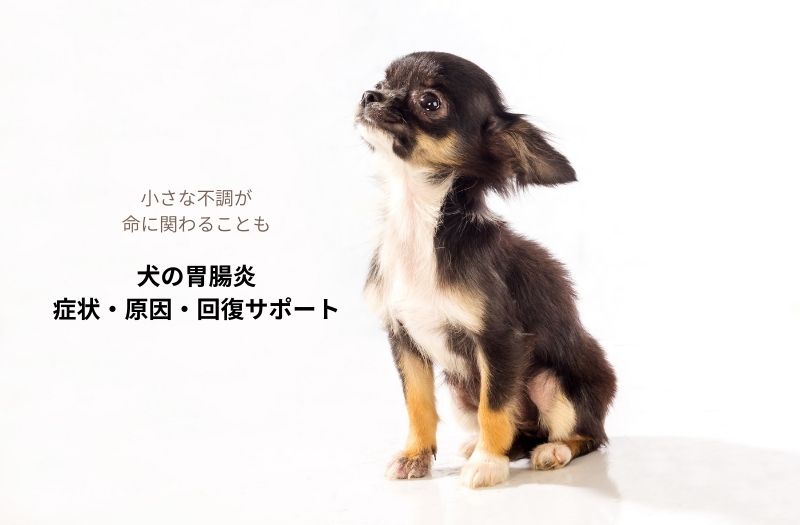
犬の胃腸炎は、嘔吐や下痢、血便などを引き起こし、飼い主さんをとても不安にさせる病気のひとつです。
急にごはんを食べなくなったり、元気がなくなる姿を見ると「自然に治るのかな」「病院へ行くべき?」と迷う方も多いでしょう。軽度であれば数日で回復する場合もありますが、重症化すると命に関わるケースもあります。
この記事では、犬の胃腸炎の原因や症状、治療の流れ、回復を支える栄養素までわかりやすく解説します。
犬の胃腸炎とは?
犬の胃腸炎は、胃や腸に炎症が起きて消化機能が乱れる病気です。症状は軽度の嘔吐や下痢から、血便や脱水を伴う重症例まで幅広く見られます。
原因も食べ物の影響から感染症、ストレスまでさまざまで、日常の中で突然発症することがあります。早期に気づいて適切に対応することが大切です。
胃腸炎の基本的な症状(嘔吐・下痢・血便など)
犬の胃腸炎では、もっとも多いのが嘔吐や下痢で、便に血が混じることもあります。水分をうまく吸収できず脱水が進む場合もあるため、症状が強いときは早めに病院で診てもらう必要があります。
特に子犬やシニア犬は体力が落ちやすく、症状が急激に悪化することがあるので注意が必要です。
急性と慢性の違い
胃腸炎には、数日で治まる「急性」と、長期間繰り返す「慢性」があります。
急性は食べ物や一時的な体調不良で起こることが多く、比較的短期間で回復するケースがあります。一方で、慢性はアレルギーや基礎疾患が隠れている可能性があり、治療や生活改善が長期にわたることもあります。
犬の胃腸炎の原因
犬の胃腸炎は、身近な食べ物から目に見えないウイルスまで、実にさまざまな要因で引き起こされます。 何が愛犬の胃腸に負担をかけているのか、主な原因を整理して予防に役立てましょう。
食べ物や異物による消化不良
フードを急に切り替えたり、人間の食べ物を口にしたことで胃腸炎を起こすケースは少なくありません。特に脂質の多い食べ物や香辛料を含む料理は犬の消化器に大きな負担を与えます。
また、誤飲した異物が胃や腸を傷つけて炎症を悪化させる場合もあり、嘔吐や血便が見られることもあります。
感染症や犬同士でうつる病気の可能性
細菌やウイルス、寄生虫による感染は、胃腸炎の非常に深刻な原因のひとつです。 特にパルボウイルスなどの感染力は非常に強く、多頭飼育の家庭やドッグラン、お散歩コースでの接触を通じて、他の犬からうつるリスクも十分に考えられます。
こうした感染性の胃腸炎は、家庭でのケアだけで治る可能性が低く、放置すると急激な脱水や体力の消耗を招き、最悪の場合は命に関わることもあります。
少しでも感染が疑われる場合は、二次感染を防ぐためにも早急に動物病院へ相談しましょう。
ストレスや環境の変化
引っ越しや生活リズムの変化、飼い主の留守などは犬にとって大きなストレスになります。精神的な負担が消化機能の乱れにつながり、胃腸炎を引き起こすことも少なくありません。
繊細な性格の犬では特に影響を受けやすく、下痢や食欲不振を繰り返すことがあります。こうした場合は生活環境の安定が重要です。
犬の胃腸炎の主な症状
犬の胃腸炎は、軽い下痢から血便や繰り返す嘔吐まで、症状の出方に幅があります。どのサインが危険なのかを知っておくことで、重症化を防ぎ、早めに適切な対応を取りやすくなります。
嘔吐が続く場合の注意点
胃腸炎では繰り返す嘔吐がよく見られます。1回で治まることもありますが、何度も続く場合は胃や腸に強い炎症が起きている可能性が高いです。
食べた物を吐き出すだけでなく、透明な液や胆汁を吐くこともあり、脱水や体力低下を招きやすいため、早めの受診が安心です。
ごはんを食べない・元気がないとき
胃腸炎にかかると、犬がごはんを食べない、遊びたがらないなどの変化が出ることがあります。食欲不振が半日以上続く場合や、ぐったりして動かない様子が見られる場合は注意が必要です。
特に子犬やシニア犬は回復力が弱く、放置すると命に関わることもあるため早めの対応が大切です。
血便や下痢が長引くケース
下痢や軟便は胃腸炎でよく見られる症状ですが、血便が出たり、数日間改善しない場合は要注意です。腸の粘膜が強く傷ついている可能性や、寄生虫・感染症が隠れているケースもあります。
長引く下痢は水分や栄養の吸収を妨げ、脱水や衰弱のリスクを高めるため、動物病院での検査と治療が必要になります。
犬の胃腸炎の治療と治し方
胃腸炎は軽度であれば自然に回復することもありますが、重症化すると命に関わる場合があります。症状の強さや持続時間に応じて、適切な治療やケアを選ぶことが大切です。
動物病院での診断と薬の使用
犬が何度も嘔吐したり血便が出ている場合は、動物病院での診断が必要です。検便や血液検査、場合によってはエコー検査で原因を特定し、整腸剤や抗生物質、点滴などが処方されます。
症状が軽いと自己判断で様子を見がちですが、薬を早めに使うことで回復を助け、二次的な合併症を防げるケースもあります。
自然に治ることはある?
軽い食べすぎや一時的な消化不良が原因なら、安静にして水分をとるだけで自然に治ることもあります。ただし、嘔吐や下痢が長引く場合や血が混じる場合は自己判断は危険です。
自然治癒を期待して放置すると脱水や体力低下を招きやすいため、症状が続く場合は必ず動物病院に相談することが安心につながります。
何日くらいで治るのか目安
急性胃腸炎の場合、治療や安静によって2〜3日で改善することが多いですが、症状や原因によって回復期間は変わります。感染症や寄生虫が関与している場合は治療に時間がかかり、1週間以上続くこともあります。
見た目では判断できないため、「何日くらい続いたら受診すべきか」という基準を持ち、長引く場合は早めに受診することが大切です。
治らない場合に考えられる病気
胃腸炎の症状がなかなか治らない場合、膵炎や腸炎、食物アレルギー、腫瘍など別の病気が隠れている可能性があります。表面的には胃腸炎と似た症状でも、根本の病気が異なれば治療法も変わります。
薬を使っても改善しないときは、早めに精密検査を受けることで、隠れた病気を発見し適切な治療へつなげることができます。
胃腸炎になったときの食事とケア
胃腸炎のときは、普段通りの生活を続けると症状が悪化することがあります。食事の与え方や散歩の有無、回復期の過ごし方を工夫することで、愛犬の体調回復を助けることができます。
食事の与え方(絶食・消化に良いごはん)
症状が軽い場合は半日〜1日の絶食で胃腸を休ませる方法が取られることもあります。ただし子犬やシニア犬は低血糖のリスクがあるため、獣医師の指示に従うことが大切です。
再開時は消化にやさしい食事を少量ずつ与え、炭水化物や脂質を抑えた柔らかいごはんが推奨されます。栄養素としては、消化吸収しやすいたんぱく質や水分補給が重要です。
散歩は控えるべきかどうか
胃腸炎で体力が落ちている犬に長時間の散歩は負担になります。無理に運動させると嘔吐や下痢を悪化させる可能性があるため、症状がある間は排泄のための短い散歩にとどめましょう。
体調が安定してきたら徐々に散歩時間を延ばし、無理なく回復を目指します。散歩よりも安静を優先することが治癒を早めるポイントです。
回復期の過ごし方
症状が落ち着いても、胃腸が完全に回復するまでには時間がかかります。再発を防ぐためには、しばらくは刺激の少ないごはんを与え、水分をしっかり補給させることが重要です。
また、ビタミンやプレバイオティクスなど腸内環境を整える栄養素を取り入れると、回復をサポートできます。無理のない生活リズムを保ち、体力が戻るのを待ちましょう。
急性胃腸炎で気をつけたいこと
多くの胃腸炎は適切なケアで回復に向かいますが、中には急激に体調が変化し、命に関わるケースも存在します 。 愛犬の小さなサインを見逃さず、落ち着いて対応するための知識を持っておきましょう。
早めの受診を考えたい危険なサイン
嘔吐や下痢が止まらず、水分をほとんど摂れない状態が続くと、犬の体力を急激に奪ってしまいます 。 特に、ぐったりして反応が鈍いときや、血便・黒色便が続くときは、消化管からの出血が疑われ、早急な対応が必要です 。
小さな体は脱水が急速に進みやすいため、「少し様子を見よう」と無理をせず、早めに獣医師さんに相談することが、愛犬を守る一番の近道になります 。
特に注意してあげたい愛犬の状態
成長期で体力のない子犬や、持病を持っていたり体力が落ちていたりするシニア犬は、胃腸炎によるダメージを強く受けやすい傾向があります 。
元気な成犬なら少し様子を見られるような症状でも、子犬やシニア犬にとっては数時間の遅れが大きな負担になることもあります 。 「いつもと何かが違う」という飼い主さんの直感を大切にして、迷ったときは迷わず病院を頼ってくださいね。
犬の胃腸炎に関するよくある質問
(タップで回答)
胃腸炎の犬は水を飲ませても大丈夫ですか?
はい、脱水を防ぐための水分補給は非常に重要です。ただし、一度にたくさん飲ませると刺激で再び嘔吐を誘発することがあるため、少量を数回に分けて与えるようにしましょう。自力で飲まない場合は、ぬるま湯でふやかしたごはんから水分を摂らせるのも効果的です。
(タップで回答)
胃腸炎のときに市販の整腸剤を与えてもいいですか?
人間用の市販薬を犬に与えるのは、成分や用量が不適切な場合があり非常に危険ですので控えましょう。犬専用の整腸剤やサプリメントもありますが、症状の原因(細菌や寄生虫など)によっては逆効果になる場合もあります。使用する際は必ず事前に獣医師へ相談してください。
(タップで回答)
胃腸炎中にシャンプーやトリミングは控えるべきですか?
はい、体調が不安定な時のシャンプーやトリミングは大きなストレスとなり、回復を遅らせる恐れがあるため控えるのが望ましいです。胃腸炎が完全に治り、体力もしっかり戻ってから行うようにしましょう。汚れが気になる場合は、お湯で絞ったタオルで優しく拭く程度に留めてください。
(タップで回答)
胃腸炎を予防する方法はありますか?
完全に防ぐことは難しいですが、日頃から急なフード切り替えを避け、人間の食べ物を与えないようにすることが基本の予防策です。また、食器を常に清潔に保ち、適度な運動と良質な食事で免疫力を落とさない生活習慣を整えることで、消化器トラブルのリスクを減らすことができます。
胃腸炎から愛犬を守るためのポイント
犬の胃腸炎は身近な病気ですが、症状や原因によっては重症化することもあります。嘔吐や下痢、血便が見られたときは軽く考えず、症状の持続時間や犬の様子をよく観察することが大切です。
早期に獣医師へ相談することで、命に関わるリスクを避けられる可能性が高まります。
また、回復を助けるには消化にやさしい食事や十分な水分補給が欠かせません。さらに、普段から急なフード切り替えを避ける、清潔な環境を保つなど、予防的な生活習慣を意識することも有効です。
日常の小さな工夫が、愛犬の健康を守る大きな支えとなります。
胃腸炎を経験した後は、お腹への負担を減らしてあげたいですよね。こちらの記事では、愛犬の胃腸を労わるためのフード選びを詳しくまとめています。

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。
ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。
成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。
愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami
愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。
参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。
本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。




