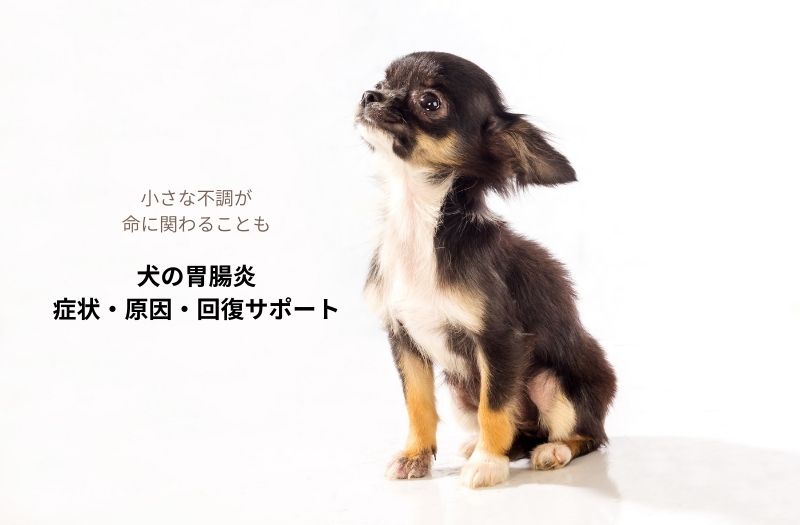犬のてんかんは、突然の発作で飼い主さんを大きく驚かせ、不安にさせる病気です。初期症状や原因、発作時の対処、治療法、寿命への影響、食事やサプリによるサポートまで、知っておきたい情報をわかりやすくまとめました。
正しい知識を持つことで、愛犬と安心して暮らすヒントになります。
発作が起きたらまずやること
突然のけいれんや意識消失を見ると、強い不安を感じてしまいますが、まずは落ち着いて愛犬の安全を守る行動が大切です。てんかん発作が起きた直後に飼い主さんが取るべき基本の対応と、すぐに病院へ相談したほうがよい目安を整理します。
安全確保とやってはいけないこと
発作が始まったら、まず周囲の家具や段差から離し、頭や体をぶつけないよう静かな場所で見守ります。無理に押さえつけたり、口の中に指や物を入れたりすると、かえってケガの原因になるため避けましょう。
声をかけ続ける必要もなく、刺激を与えず静かに発作が治まるのを待つことが基本です。発作中は体が熱くなりやすいため、長引く場合はタオルで体を包みつつ、体温の上昇にも注意して見守ることが大切です。
受診の目安と記録のコツ(動画・時間)
発作が数分以上続く(目安として5分前後)、短時間に何度も繰り返す、意識が戻りにくい場合は緊急性が高い可能性があります。まずは動物病院へ連絡し、受診の要否を相談しましょう。
落ち着いて対応するためにも、発作の開始と終了の時間を測り、可能であればスマートフォンで動画を撮影しておくと診察時の大きな手がかりになります。
発作の頻度や前後の様子、食事や行動の変化をメモしておくことで、原因の特定や治療方針の判断に役立ちます。
てんかんとは?犬で起こる仕組み
犬のてんかんは、脳の神経が一時的にうまく働かなくなることで起きる発作のことです。突然のけいれんや硬直はとても驚きますが、てんかん自体は珍しい病気ではありません。
正しい知識を持つことで、発作があっても愛犬と安心して暮らす工夫ができます。
てんかん発作の基本と神経の異常
犬の脳には、体を動かすための電気信号を送る神経細胞が無数にあります。てんかんは、その信号が一斉に暴走してしまうことで発作が起きる状態です。症状は全身けいれん、体の硬直、よだれ、意識の一時的な消失などさまざま。
発作は数秒から数分で治まることが多いですが、まれに長引くこともあります。発作がどんな状況で起きたかを覚えておくと、あとで原因を探るヒントになります。
似た症状との違い
一見てんかんに見えても、低血糖や心臓のトラブル、中毒などが似た症状を示すことがあります。
たとえば低血糖では、ふらつきやけいれん、失神が起こることがあり、区別が難しい場合も。迷ったときは動画やメモを残しておくと、診断に役立ちます。
てんかん発作とよく似た動きを見せる病気の一つに、血糖値が急激に下がる「低血糖」があります。見分けがつきにくいことも多いため、判断を誤らないよう基礎知識を押さえておくと安心です。
初期症状と発作のサイン
犬のてんかんは、発作そのものだけでなく、始まる前の小さな変化にも気づけるかどうかが大切です。前兆を知っておくと、飼い主さんが冷静に準備でき、愛犬の安全を守りやすくなります。
前兆で見られる行動や仕草
発作の少し前、犬が落ち着きを失ってウロウロ歩き回ったり、急に飼い主さんにくっついてきたりすることがあります。よだれを垂らす、震える、遠くをじっと見つめるといった動きも前触れの一つ。
これらの変化は数分から数時間前に現れることがあり、発作のサインとして覚えておくと、周囲を片づけたり危険を避けたりする準備ができます。
発作中・発作後の特徴と頻度
発作が始まると、体が硬直したり、全身がけいれんしたり、意識を失って倒れたりすることがあります。よだれや泡を吹く、排尿・排便があるケースも。多くは数秒〜数分で治まりますが、まれに5分以上続くこともあります。
発作後は混乱して徘徊したり、ふらついたり、極端に空腹になることがあり、しばらく様子を見守ることが大切です。発作がどんなタイミングでどれくらいの長さで起きたかを控えておくと、後のケアや診断に役立ちます。
てんかんの原因と悪化要因
犬のてんかんにはさまざまな要素が関わっており、体質や環境が複雑に影響します。原因や誘因を理解しておくことで、日常のケアに活かしやすくなります。
遺伝・脳の障害・ストレスなどの主な要素
てんかんの多くは「特発性てんかん」と呼ばれ、はっきりした原因が特定できないものです。遺伝が関与しているケースもあれば、脳腫瘍や炎症、外傷、代謝異常などで発作が起きることもあります。
さらに、睡眠不足や大きな音、急な環境の変化などストレスが誘因になる場合も。できる範囲で生活のリズムを整え、刺激を減らす工夫が安心につながります。
食べ物やさつまいもとの関係
さつまいもは、食物繊維やビタミンが豊富で、犬にとって安全な食材として広く利用されています。てんかんを悪化させる明確な根拠はなく、適量であれば健康的なおやつや栄養補給に役立ちます。
ただし、どんな食材も急に大量に与えると体調を崩す可能性があります。普段のカロリー内で少しずつ試しながら与え、発作があった際には「いつ・何をどれだけ食べたか」を記録しておくと、原因を考える手がかりになります。
てんかん発作時の対処と動物病院での治療
発作を目の当たりにすると動揺してしまいますが、落ち着いて行動できるかが愛犬を守る鍵になります。安全を確保し、適切なタイミングで専門家に相談できるよう、ポイントを覚えておきましょう。
自宅でできる応急対応と連絡の目安
発作が始まったら、まず犬の周囲から家具や尖った物をどけ、ケガを防ぎます。口の中に物を入れたり、体を無理に押さえつけたりしないでください。多くの場合、発作は数秒〜数分で収まります。
5分以上続く、もしくは短時間で何度も繰り返すときは緊急性が高いため、動物病院へ連絡を。動画やメモで発作の様子を残すと、原因特定に役立ちます。
動物病院による治療法と薬の副作用
てんかん治療には、フェノバルビタールや臭化カリウムなどの抗てんかん薬が使われます。薬は発作を完全になくすのではなく、頻度と重さを減らすことが目的です。
副作用として、眠気、ふらつき、多飲多尿、肝酵素の上昇などが見られる場合があります。服薬中に不安を感じたら、勝手に中止せず、処方を受けた担当医に相談して用量や薬の変更を検討してください。
食事とサプリによるサポート
てんかんを完全に防ぐ食事はありませんが、体に優しいメニューや栄養補助で健康を支えることはできます。毎日のごはんと小さな工夫が、愛犬の暮らしを安定させる手助けになります。
食事選びと日常の工夫
高品質なたんぱく質とバランスの取れた脂肪を含むフードを選び、人工添加物や過剰な糖分は避けるのが無難です。水分補給をしっかり確保し、フードを切り替えるときは急がず少しずつ混ぜて移行しましょう。
てんかんを抱える愛犬に合ったフードを選ぶことは、日常の安心につながります。発作を治すものではありませんが、神経や脳をサポートする栄養素を含むフードを取り入れることで、より健やかな暮らしを支えやすくなります。
てんかんの子のフード選びでどのフードなら使いやすいか、療法食と一般食のどちらを選ぶべきかなど、具体的な商品選びで悩む飼い主さんも多いと思います。
てんかんに配慮した栄養素や選び方のポイント、市販で試しやすいフードをまとめた記事もあるので、フード選びを一から見直したいときに役立ててください。
栄養補助サプリの上手な取り入れ方
MCTオイルやオメガ3脂肪酸、ビタミンB群など、一部のサプリは神経の健康維持を助ける可能性があります。与えるときは、犬用として安全が確認されている製品を選び、少量からスタートしてください。
与えすぎや人間用サプリの流用は思わぬ不調の原因になることも。あわせて 体調変化の原因にもなる犬の誤食リスク(人間の食べ物) を確認しておくと安心です。
てんかんのリスクが高い犬種
てんかんはどの犬にも起こり得ますが、特定の犬種や体格でやや発生しやすい傾向が知られています。犬種=必ず発症ではないことを理解したうえで、体質的なリスクを把握しておくと安心です。
発症しやすい犬種と体格の特徴
ビーグル、ダックスフンド、プードル、シェットランド・シープドッグ、ゴールデン・レトリバー、シェパード系などは、統計上てんかんの報告が多いとされています。
小型〜中型犬の一部で特に目立つ傾向がありますが、大型犬でも例外ではありません。体質を理解した上で、日常のちょっとした変化にも目を配ることが大切です。
神経系の遺伝的素因が報告され、特発性てんかんの症例が多い犬種です。
小型犬の中では比較的発症例が多く、脳の構造的な特徴や遺伝が関与すると考えられています。
家系的に特発性てんかんを持つラインが知られており、若い年齢で初発する傾向があります。
家系的に特発性てんかんを持つラインが知られており、若い年齢で初発する傾向があります。
大型犬の中でも症例が報告されており、免疫系や代謝系の異常が引き金になることも。
警察犬・作業犬として選抜繁殖された経緯から、神経疾患の遺伝的リスクが指摘されています。
最新の研究では、同じ犬種内でも血統や系統によって発症率が異なることが示唆されており、生活環境やストレス管理も重要とされています。
出典
Idiopathic Epilepsy Risk Allele Trends in Belgian Tervuren(2024)
ADAM23 is a common risk gene for canine idiopathic epilepsy(2017)
病気の予防や早めのケアは、長生きにもつながります。ミックス犬は体格や体質の幅が広いので、ミックス犬の寿命と長生きの考え方も参考にしてみてください。
年齢・性別など他のリスク要因
初めての発作が1〜5歳で現れることが多く、この時期に繰り返す発作があれば、特発性てんかんの可能性が高まると言われます。
性別による大きな差はありませんが、一部の報告ではオスでやや多い傾向があるとのデータも。発症年齢の目安を知っておくと、体調の変化に気づきやすくなります。
寿命・予後と生活の工夫
てんかんを持つ犬でも、発作をうまくコントロールできれば長く元気に暮らしている子がたくさんいます。発作の頻度や重さを理解し、日常の工夫で安心できる環境を整えましょう。
発作と寿命・死亡リスクの考え方
発作が年に数回以下で安定していれば、寿命は健康な犬とほぼ変わらないとされています。
逆に、群発(短時間で何度も発作が起きる)や重積(5分以上発作が続く)は危険で、早めの受診が必要です。死亡リスクを減らすには、発作のパターンを把握し、生活の中で無理をさせないことが大切です。
ストレス軽減と暮らしの改善ポイント
規則正しい生活リズムと十分な休息、音や光などの刺激を減らす工夫が、発作の誘因を減らすサポートになります。激しい運動や急な環境変化は避け、安心できる場所を用意することがポイント。
発作後は静かに見守り、体を温めたり水を与えたりして、穏やかに回復を促してあげましょう。
てんかんは治る?再発と完治の可能性
てんかんは「一度治療したら終わり」という病気ではありません。けれども、発作の回数を減らしたり、長く安定した生活を送っている犬はたくさんいます。
コントロール可能なケースと注意点
多くの犬では、適切な薬や生活の工夫によって発作を数か月~数年単位で抑えることができます。完治が難しい場合でも、発作の間隔が長くなれば、日常生活に大きな支障をきたさずに過ごせることがほとんどです。
ただし、自己判断で薬を減らしたりやめたりすると、重い発作が起きる危険があります。薬の量や種類を変えるときは、必ず獣医に相談してください。
再発防止に意識したい日常ケア
十分な休息と規則正しい生活リズム、ストレスを減らす工夫は、再発を防ぐうえで大切です。大きな音や急な環境変化を避け、穏やかな環境を用意することがポイントです。
体調や発作の様子を日記やアプリで記録しておくと、再発の傾向を早くつかむ手助けになります。
てんかんとの暮らしを支えるヒント
犬のてんかんは、発作が突然起こるため不安になりやすい病気ですが、原因や初期症状、対処法を知っておくことで、愛犬の安全と生活の質を守ることができます。
・前兆サインを理解し、危険物を片づけて発作時の安全を確保すること
・発作の頻度や持続時間、発作前後の行動を記録しておくこと
・適切な食事やサプリ、ストレスを減らす環境づくりが、長期的なサポートになること
・リスクの高い犬種や若齢期に初発する傾向を把握し、異変を早めに気づくこと
てんかんがあっても、上手にコントロールすれば健康な犬と同じように長く暮らしている子はたくさんいます。 正しい知識と日々の小さな工夫が、飼い主さんと愛犬の安心につながります。

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。
ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。
成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。
愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami
愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。
参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。
本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。