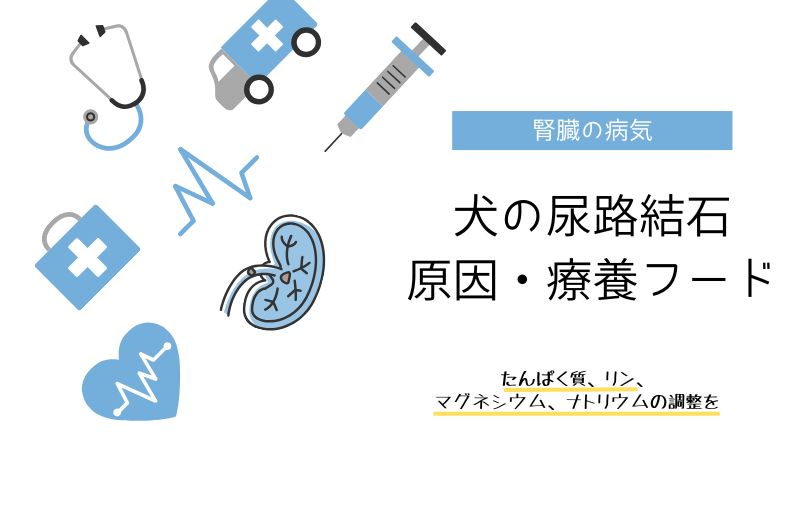
「愛犬が血尿を出した」「何度もトイレに行くのにおしっこが出ない…」
犬の尿路結石(ストルバイト・シュウ酸カルシウム)は、強い痛みを伴うだけでなく、非常に再発しやすい厄介な病気です。
動物病院で治療を受けて「治った!」と思っても、これまでの食事や生活習慣を見直さなければ、すぐにまた結石ができてしまうことも少なくありません。
この記事では、尿路結石の再発を防ぐための「ドッグフードの選び方」や、良かれと思って与えがちな「絶対に避けたいNGな食べ物」、そしてご自宅でできる食事ケアの工夫をわかりやすく解説します。
尿路結石の犬に「絶対に避けたい」食べ物・おやつ
結石の再発を防ぐ第一歩は、「結石の材料になるものを与えないこと」です。普段のおやつや手作りトッピングで、以下のような食材を与えていないかチェックしてみましょう。
ミネラルが豊富な「煮干し・海藻類」は要注意
犬用のおやつとして人気の「煮干し」や「小魚のジャーキー」は、カルシウムやマグネシウム、リンなどのミネラルが非常に豊富です。
健康な犬には良い栄養源ですが、尿路結石(特にストルバイト結石)の犬にとっては、結石の材料を直接食べているようなものなので、避けるのが無難です。
シュウ酸を多く含む「ほうれん草・さつまいも」
手作りごはんでよく使われる「ほうれん草」や「さつまいも」「ブロッコリー」には、シュウ酸が多く含まれています。
これらは「シュウ酸カルシウム結石」の原因になりやすいため、尿路結石の治療中・予防中の犬には与えないか、与える場合は必ず茹でて茹で汁をしっかり捨てるなどの工夫が必要です。
良かれと思って与えがちな「ミネラルウォーター」
「愛犬には美味しい水を」と、人間用のミネラルウォーターを与えていませんか?
実は、硬水タイプのミネラルウォーターにはカルシウムやマグネシウムが多く含まれており、結石のリスクを高めてしまいます。犬の飲み水は、日本の一般的な「水道水(軟水)」が一番適しています。
【種類別】尿路結石に配慮したドッグフードの選び方
尿路結石には主に「ストルバイト」と「シュウ酸カルシウム」の2種類があり、それぞれ原因となる尿のpH(酸性・アルカリ性)が異なります。フード選びを間違えると逆効果になるため、必ず獣医師の診断結果に合わせて選びましょう。
ストルバイト結石とシュウ酸カルシウム結石の違い
・ストルバイト結石:尿が「アルカリ性」に傾くとできやすい。食事療法で溶かすことができるケースが多い。
・シュウ酸カルシウム結石:尿が「酸性」に傾くとできやすい。一度できると食事では溶かせないため、手術と再発予防が基本。
療法食と総合栄養食(ケア用)の違いを理解する
すでに結石ができている、または治療直後の場合は、必ず獣医師から処方される「療法食」を与えてください。療法食はミネラルバランスが厳密に計算されています。
一方、市販の「下部尿路ケア(総合栄養食)」と書かれたフードは、あくまで健康な犬の「予防・維持用」です。自己判断で療法食からケア用フードに切り替えると、再発のリスクが高まります。
フード選びで意識したい「4つの栄養素」
結石ケアの療法食やサポートフードは、主に以下の成分バランスが緻密に調整されています。これらの栄養素のコントロールが再発防止の鍵を握ります。
- リン・マグネシウム:結石の直接的な材料になるため、過剰摂取はNGです。
- タンパク質:摂りすぎると尿中のアンモニア(老廃物)が増え、ストルバイト結石の原因になります。適度な制限が必要です。
- ナトリウム:療法食の中には、あえてナトリウムを少し多めにし、お水をたくさん飲ませて尿を薄める工夫がされているものがあります。(※心臓や腎臓に疾患がある犬の場合は注意が必要です)
注意!「クランベリー」が逆効果になる結石もある
膀胱炎のケアとして有名な「クランベリー」ですが、尿路結石の犬に与える際は要注意です。
クランベリーは尿を酸性に傾ける働きがあるため、アルカリ性でできる「ストルバイト結石」のケアには有効な場合があります。しかし、酸性でできる「シュウ酸カルシウム結石」の犬に与えると、結石を悪化させてしまう危険があります。
サプリやケアフードを選ぶ際は必ず確認しましょう。
尿路結石のケア・再発防止におすすめのドッグフードと療法食
結石の種類や治療段階に合わせて、適切な食事を選びましょう。
【獣医師推奨】結石ケアの定番・療法食
動物病院でよく処方される、信頼と実績のある療法食です。どちらの結石タイプにも対応できるようpHが調整されているものが主流です。

ストルバイト結石の溶解と再発防止、さらにシュウ酸カルシウム結石の形成リスクにも配慮された、動物病院でも定番の療法食です。
結石の材料となるミネラル(リンやマグネシウム、カルシウムなど)が厳密に調整されており、尿のpHを適切なバランスに保つよう設計されています。毎日飽きずに食べてくれるよう、チキン味などで嗜好性が高く作られているのも特徴です。

「尿量を増やすこと」に重点を置いて開発された療法食で、少し多めのナトリウムを含ませることで自発的な飲水を促し、結石の原因成分を尿と一緒に洗い流す(ウォッシュアウト)ことをサポートします。
ストルバイト結石の溶解はもちろん、シュウ酸カルシウム結石の予防にも対応しています。小型犬の小さな口でも食べやすいよう、粒のサイズが工夫されているのも嬉しいポイントです。
※療法食は必ずかかりつけの獣医師の指導のもとで与えてください。
【水分補給】トッピングに使えるウェットフード・スープ
療法食のドライフードだけでは水分が不足しがちな場合や、食いつきが悪い場合は、同じシリーズの「ウェットタイプ(缶詰やパウチ)」をトッピングするのが最も安全で確実な方法です。
市販のおやつやスープを足してしまうと、せっかくの療法食のミネラルバランスが崩れてしまうため注意しましょう。
結石を再発させない!日々の食事と生活の工夫
ドッグフードの見直しと並行して取り組みたいのが、毎日の生活習慣のケアです。結石は体質的な要因も大きいですが、お水の飲み方や運動不足といった日々の小さな積み重ねが再発の引き金になることも少なくありません。
ご自宅で今日からすぐに始められる、再発防止のための具体的な工夫をご紹介します。
お水をたっぷり飲ませるアイデア
尿路結石の最大の予防法は「おしっこの量と回数を増やして、結晶を洗い流すこと」です。
- ドライフードをぬるま湯でふやかして与える
- 水飲み場を家の中に複数(3箇所以上)設置する
- 冬場は水が冷たすぎると飲まないので、少しお湯を足して「ぬるま湯」にする
ぽっちゃり体型は要注意?適正体重の維持
肥満気味の犬は、動くのが億劫になり、水を飲む回数もトイレに行く回数も減ってしまいます。おしっこを我慢する時間が長くなると、尿が濃縮されて結石ができやすくなります。
散歩や遊びで適度に運動し、適正体重を保つことも立派な結石予防です。
犬の尿路結石に関するよくある質問
尿路結石は再発しやすい病気であるため、飼い主の方から寄せられる疑問も多くあります。ここでは特に多い質問をまとめました。
(タップで回答)
尿路結石は季節によって発症しやすさが変わりますか?
夏場は飲水量が減りやすく、尿が濃くなることで結石ができやすくなる傾向があります。反対に冬は活動量が落ちるため、代謝の低下や排尿回数の減少がリスクにつながります。季節ごとに水分補給や散歩の工夫をしてあげることが大切です。
(タップで回答)
手作り食は尿路結石に良いですか?
手作り食は水分を多く含めることができるメリットがありますが、栄養バランスが崩れやすく、シュウ酸やミネラルを過剰に含んでしまうリスクもあります。ご自宅でのケアは『結石対応の総合栄養食や療法食』をベースにするのが最も安全です。
(タップで回答)
尿路結石の犬におやつはあげてもいいですか?
ミネラル(リンやマグネシウム)を多く含む煮干しやジャーキーは結石の原因になりやすいため控えるのが無難です。療法食メーカーが出している結石配慮用のおやつなどを選び、与える量は担当の獣医師に相談しましょう。
まとめ|愛犬の結石タイプに合った正しい食事管理を
犬の尿路結石は、食事と生活習慣の改善で再発リスクを大きく減らすことができます。
- 煮干しやさつまいも、ミネラルウォーターなどNGな食材を避ける
- 自己判断せず、結石の種類に合った療法食を与える
- 何よりも「水分補給」を優先し、おしっこを我慢させない
愛犬が痛い思いを繰り返さないよう、今日からの食事管理や水飲みの工夫をぜひ実践してみてくださいね。

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。
ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。
成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。
愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami
愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。
参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。
本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。




