
「動物病院の健診で心臓に雑音があると言われた」 「最近、愛犬が夜中や朝方に『カッカッ』という咳をするようになった」
そんな症状から病院を受診し、「僧帽弁閉鎖不全症(そうぼうべんへいさふぜんしょう)」と診断されて不安を抱えている飼い主さんは非常に多いです。
チワワやプードルなどの小型犬に非常に多いこの病気は、一度発症すると完治することはありません。しかし、悲観しないでください。
早期発見とお薬、そして**「毎日の食事管理(塩分制限)」**を適切に行うことで、進行を遅らせ、愛犬と穏やかに過ごす時間を延ばすことは十分に可能です。
この記事では、僧帽弁閉鎖不全症の進行ステージに合わせた食事の選び方や、心臓への負担を減らすドッグフード、そして知っておきたい病気との付き合い方について詳しく解説します。
僧帽弁閉鎖不全症の食事管理「3つの基本」
心臓病の犬にとって、食事は単なる栄養補給ではなく「治療の一環」です。心臓のポンプ機能が弱まっている愛犬のために、まずは食事選びの3つの鉄則を押さえましょう。
① 心臓の負担を減らす「塩分(ナトリウム)制限」
最も重要なのが「減塩」です。塩分(ナトリウム)を摂りすぎると、体内の水分量が増えて血圧が上がり、弱った心臓にさらに大きな負担をかけてしまいます。
人の食事やおやつを与えるのは絶対にNGです。ドッグフードを選ぶ際も、ナトリウム含有量が調整されたもの(目安として0.3%以下など)を選ぶのが理想的です。
② 筋肉とエネルギーを維持する「良質なタンパク質」
心臓病が進行すると、エネルギー消費が激しくなり、筋肉が落ちて痩せてしまう「心臓悪液質(しんぞうあくえきしつ)」という状態になりやすくなります。
腎臓病を併発していない限り、心臓病の犬には「良質で消化の良いタンパク質」をしっかり与えて、体力を維持させることが重要です。
③ 血液の流れを助ける「オメガ3脂肪酸・タウリン」
血液をサラサラにして炎症を抑える「オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)」や、心筋のエネルギー代謝を助ける「タウリン」「L-カルニチン」などの成分も、心臓ケアフードには欠かせません。
【初期〜進行度別】心臓ケアにおすすめのドッグフード5選
「心臓サポート」と書かれたフードはたくさんありますが、愛犬の病気の進行度(ステージ)に合わせて選ぶことが大切です。ここでは代表的な5つのタイプを紹介します。
【療法食】進行したステージの子に(獣医師推奨)
すでに心拡大が進んでいる場合は、獣医師と相談のうえで専用の療法食を選びましょう。

心臓に配慮が必要な犬のための療法食です。ナトリウム量を調整し、EPA・DHAやタウリンなどを配合。毎日の食事から心臓の健康維持をやさしくサポートし、体調管理を続けたい飼い主さんにも選びやすい設計です。
【初期・予防】低ナトリウムの市販プレミアムフード
「雑音はあるけれど、まだ薬は必要ない」という初期段階(ステージB1)なら、療法食までは必要ないこともあります。良質な市販フードの中から、ナトリウム値が低めのものを選びましょう。
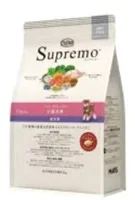
シュプレモは、自然素材にこだわった総合栄養食で、心臓の健康維持に役立つタウリンやオメガ3脂肪酸も配合。ナトリウムは約0.25%と一般的なフードよりやや低めに設計されています。
食いつきも良好で、食欲が落ちがちな心臓病の子にも使いやすいのが魅力です。
リンク

加水調理による低温製法で栄養価と消化のやさしさを両立したPLATINUM。
ナトリウム含有量は0.21%と抑えられており、心臓に負担をかけたくない犬にも向いています。余計な添加物を使用せず、自然な香りと食感で食いつきにも定評があります。
リンク

心臓サポート設計の療法食で、ナトリウム量をしっかり制限しつつ、タウリンやL‑カルニチンを配合。過剰な体液貯留(浮腫)を防ぎながら、心筋の機能維持をサポートします。
穀物不使用グレインフリーフードで、アレルギー対応にも◎。まずは800gサイズで体調観察後、継続購買するのがおすすめです。
リンク
シニアに配慮した心臓サポートフード
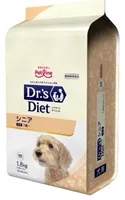
高齢犬の健康維持をサポートするために設計された「ドクターズダイエット シニアエイジングエイド」は、ナトリウム含有量約0.23%と控えめで、心臓病のケアにも活用しやすい減塩設計が特徴です。
消化に配慮された栄養バランスで、食欲や体力が落ちやすいシニア期でも無理なく続けられるフードです。動物でも取り扱いがある商品なので、安心感も高いのが魅力です。
リンク
食いつきが悪い時の工夫とサプリメント
心臓病の子は食欲にムラが出ることがあります。そんな時は、フードを人肌程度に温めて香りを立てたり、塩分無添加の鶏の茹で汁をかけてあげてください。
「今のフードを変えたくない」という場合は、いつもの食事に心臓ケア用のサプリメントをプラスする方法もあります。
知っておきたい「僧帽弁閉鎖不全症」の症状とステージ
僧帽弁閉鎖不全症は、心臓の左心房と左心室の間にある「僧帽弁」がうまく閉じなくなり、血液が逆流してしまう病気です。
「咳・疲れやすい」はサイン。ステージ別の症状
病気の進行度は一般的に「ステージA〜D」で分類されます。
- ステージA(リスク群): 症状はないが、キャバリアやチワワなど発症しやすい犬種。
- ステージB(初期): 心雑音は聞こえるが、症状はない(B1)〜心臓拡大が見られる(B2)。
- ステージC(心不全期): 肺水腫などの症状が出ており、咳が出る、疲れやすい、呼吸が荒いなどのサインが見られる。
- ステージD(末期): 薬の効きが悪くなり、安静時でも呼吸が苦しい状態。
進行を遅らせるために:飼い主ができる日々のケア
「余命」について検索し、不安になる飼い主さんは多いですが、この病気は個体差が非常に大きいです。
ステージB2(心拡大)の段階から適切な投薬と食事管理を始めれば、症状が出るまでの期間(無症状期)を大幅に延ばせることがわかっています。
「何歳まで生きられるか」という数字よりも、「今日の愛犬をどう楽にしてあげるか」に目を向けてケアを続けましょう。
心臓病の原因は「歯周病」?意外なリスクと予防
実は、僧帽弁閉鎖不全症を悪化させる隠れた要因として「歯周病」が指摘されています。
歯周病菌が血管に入り込み、全身を巡って心臓の弁に付着すると、炎症を引き起こして弁の変形を早めてしまうリスクがあるのです。
心臓が悪くなってからでは全身麻酔を使った歯石除去が難しくなるため、愛犬が元気なうちから、または心臓病と診断された後でもできる範囲で、口内ケアを続けることが心臓を守ることにつながります。
➡ 犬の歯周病は食事とケアで防ぐ!口臭や歯石対策とフードの選び方
※心臓のためにも重要な、自宅でできる歯周病ケアについてはこちら。
僧帽弁閉鎖不全症で気になることQ&A
僧帽弁閉鎖不全症と向き合う中で、日常生活のちょっとした判断に迷う場面は少なくありません。病気そのものよりも、毎日の過ごし方やケアについて悩む飼い主の方も多いのではないでしょうか。
実際によく聞かれる疑問をもとに、生活に役立つ考え方をまとめました。
(タップで回答)
心臓病の犬でも散歩はしていいですか?
散歩が必ずしも禁止されるわけではなく、体調に合わせて続けられるケースもあります。大切なのは距離や時間にこだわらず、その日の様子を見ながら無理をさせないことです。歩くペースが落ちたり、立ち止まる回数が増えた場合は、早めに切り上げるなど柔軟に対応することで安心につながります。
(タップで回答)
僧帽弁閉鎖不全症でもシャンプーはできますか?
体調が安定している日であれば、シャンプーが可能な場合もあります。ただし、体力を使いやすいため、お湯の温度をぬるめにし、短時間で終わらせる工夫が大切です。少し元気がない日や呼吸の様子が気になるときは、無理をせず日を改める判断が安心につながります。
(タップで回答)
元気そうに見えても注意したほうがいいですか?
見た目が元気でも、体の内側では変化が進んでいることもあります。ただし、常に不安を抱く必要はありません。普段の様子を基準に、散歩後の回復の早さや呼吸の落ち着き方などを比べることで、小さな変化に気づきやすくなります。
まとめ:毎日のごはんで心臓をいたわる生活を
僧帽弁閉鎖不全症は「うまく付き合っていく病気」です。診断されても、すぐに普通の生活ができなくなるわけではありません。
- 塩分(ナトリウム)を控えた食事を選ぶ
- ステージに合わせた療法食や薬を適切に取り入れる
- 歯周病ケアも忘れずに行う
日々の小さなお皿の上から、愛犬の心臓をサポートしてあげましょう。
▼ あわせて読みたい
大型犬に多い「拡張型心筋症(DCM)」の場合は、食事の選び方や注意点が少し異なります。
➡ 犬の拡張型心筋症(DCM)とは?原因・初期症状から治療法や余命まで徹底解説

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。
ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。
成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。
愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami
愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。
参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。
本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。




