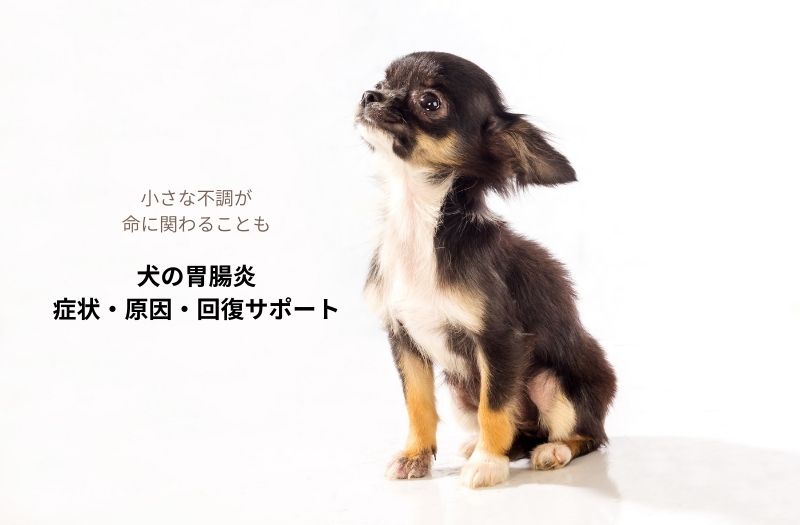愛犬の目が白く濁ってきたように見えると、「もしかして白内障…?」と心配になる飼い主さんも多いでしょう。白内障は加齢によるものが多いですが、若い犬や特定の犬種でも起こることがあります。
進行すると視力が低下し、生活の質や寿命にも影響する可能性があるため、早期の発見とケアが大切です。
この記事では、白内障の初期症状や治療法、手術費用、予防につながる食べ物や生活習慣まで、わかりやすく解説します。
犬の白内障とは?
白内障は水晶体が白く濁り、視力が低下していく病気です。加齢性のものから遺伝や外傷など原因はさまざまで、犬にとって大きな負担となります。
白内障の主な原因
犬の白内障で最も多いのは加齢によるものです。年齢を重ねると水晶体のたんぱく質が変化し、透明だった部分が白く濁っていきます。
また、糖尿病や目の炎症、外傷も原因になり得ます。放置すると進行が早まり、視力を失う危険性もあるため、飼い主が原因を理解しておくことが大切です。
加齢以外で発症するケース(糖尿病や外傷など)
白内障はシニア犬だけでなく若い犬にも発症します。代表的な原因は糖尿病で、高血糖状態が続くと水晶体内部で代謝異常が起こり、短期間で急速に白濁することがあります。
さらに目の外傷や炎症によって水晶体が傷つき、年齢に関係なく白内障が進行することもあるため、早期の発見と治療が重要です。
初期症状と見分け方
白内障はゆっくり進行するため、初期段階では見逃されやすい病気です。早めに気づけるかどうかが、進行を抑える上でとても大切なポイントになります。
よく見られる初期症状
初期の白内障では、黒目がうっすら白く霞み、光の当たり方で透明感が減って見えることがあります。暗所を怖がる、散歩中に段差でつまずく、物や壁にぶつかりやすいなどの行動変化もサインです。
数日〜数週間続く違和感は動画や写真で記録し、早めに動物病院で検査を受けましょう。放置は進行を招きます。
飼い主が家庭で気づきやすい変化
家のなかでは、階段を降りるのをためらう、ソファの縁を踏み外す、いつものおもちゃを見つけにくい、といった小さな変化が手がかりになります。
昼夜で見え方が変わる、強い光を眩しがる、顔を近づけて匂いで確かめる動作が増えるのも要注意。行動メモを残し、受診時に伝えましょう。動画も有効です。
白内障を放置するとどうなる?
白内障は自然に治る病気ではなく、進行すれば視力を失う危険があります。放置すると愛犬の生活に大きな影響を与えるため、早めの対応が大切です。
進行による生活の不自由さ
白内障が進行すると、光を感じる程度しか見えなくなり、散歩や室内での移動が困難になります。家具にぶつかる、階段を怖がるなど、日常の行動にも支障が出ます。
見えないことによる不安から吠えやすくなったり、活動量が減って寝ている時間が増えるケースもあります。心身ともに負担が大きいため、放置は望ましくありません。
合併症や寿命への影響
白内障を放置すると、水晶体の炎症がきっかけで緑内障やぶどう膜炎といった合併症を引き起こすことがあります。これらは強い痛みを伴い、視力を完全に失うだけでなく、食欲低下やストレスによって寿命を縮めるリスクも高まります。
発見が遅れるほど治療は難しくなるため、早期対応が愛犬の健康と生活を守る大切な手段になります。
治療方法と目薬の役割
白内障の治療法は症状の進行度や犬の年齢、全身状態によって異なります。点眼薬での進行抑制から外科的な手術まで、選択肢を理解することが大切です。
点眼薬でできることと限界
点眼薬は白内障の進行を遅らせる効果が期待できますが、すでに濁ってしまった水晶体を透明に戻すことはできません。抗酸化成分や代謝をサポートする成分が配合された薬が使われることが多く、初期や予防的な段階で役立ちます。
ただし、毎日の投与と継続的な管理が欠かせず、根本治療にはならない点を理解しておくことが大切です。
手術で視力を取り戻せるケース
白内障が進行して視力を失ってしまった場合、唯一視力を取り戻せる治療が外科手術です。水晶体を取り除き、人工レンズを挿入することで再び物が見えるようになります。
成功率は比較的高く、手術後に元気を取り戻す犬も多いですが、全身麻酔のリスクや高額な費用、術後のケアも必要です。獣医師とよく相談し、愛犬に合った方法を選びましょう。
白内障手術の費用と注意点
白内障の手術は犬にとって大きな治療ですが、視力を取り戻せる唯一の方法とされています。費用や術後ケアについて理解し、検討することが大切です。
費用の目安(片眼・両眼)
犬の白内障手術は高度な医療技術を必要とするため、費用は高額です。片眼で20〜30万円、両眼では40〜60万円ほどが目安とされます。病院や地域によって差があり、検査費や入院費、術後の点眼薬代が加わる場合もあります。
経済的な負担は大きいですが、愛犬の快適な生活を取り戻せる可能性があるため、事前に見積もりを確認して準備することが大切です。
手術に向いている犬・向いていない犬
白内障手術はすべての犬に適しているわけではありません。体力が十分にあり、全身麻酔に耐えられる健康状態の犬は手術に向いています。
一方で、心臓病や腎臓病を抱えている犬、高齢で麻酔リスクが高い犬は避けた方が良い場合もあります。また、手術後には数週間〜数ヶ月のケアや点眼管理が必要で、飼い主がしっかり対応できる環境であることも重要です。
予防のためにできる食べ物や習慣
白内障は完全に防げる病気ではありませんが、日常の食事や生活習慣を整えることで進行を遅らせたりリスクを軽減することが期待できます。
抗酸化成分を含む食材(ブルーベリー・ルテインなど)
白内障は酸化ストレスが原因のひとつと考えられており、抗酸化成分を含む食材は予防のサポートになります。ブルーベリーに含まれるアントシアニンや、ほうれん草などに含まれるルテインは目の健康を守る働きがあるとされます。
これらをフードやサプリで補うことで、白内障の進行を遅らせる効果が期待できます。ただし与えすぎず、獣医師に相談しながら取り入れることが安心です。
日常生活での予防習慣
紫外線は目の老化を進める要因のひとつといわれています。散歩の時間を朝や夕方の涼しい時間帯にずらしたり、日差しの強い時間を避ける工夫が役立ちます。
また、肥満や糖尿病は白内障の発症リスクを高めるため、適切な体重管理や栄養バランスの取れたフード選びも大切です。日々の小さな積み重ねが、愛犬の目の健康を守る力になります。
白内障になりやすい犬種
すべての犬に起こり得る病気ですが、遺伝的に白内障のリスクが高い犬種も知られています。愛犬の体質を理解することで、早期の発見や予防につながります。
小型犬で気をつけたい犬種
小型犬の中では、トイプードルやシー・ズー、ミニチュア・ダックスフンドなどが白内障になりやすい犬種として知られています。遺伝的要因の影響を受けやすく、若い頃から発症するケースも少なくありません。
普段の生活で目の濁りや行動の変化を見逃さないことが大切です。定期的に動物病院で目の検診を受けると、早期発見につながります。
・トイプードル:遺伝性白内障が多く、若齢でも発症するケースが報告されています。
・シー・ズー:目が突出気味で乾燥や外傷のリスクが高く、それが白内障を早める要因になることがあります。
・ミニチュア・ダックスフンド:遺伝的に目の病気が出やすく、若いうちから白内障になるケースが多い犬種です。
中大型犬で注意したい犬種
中大型犬では、ラブラドール・レトリーバーやゴールデン・レトリーバー、シベリアン・ハスキーなどが白内障の発症リスクが高いといわれています。これらの犬種は加齢による発症が多い一方、遺伝的に若い年齢で発症することもあります。
体格が大きいため視力を失うと行動制限が大きくなりやすく、飼い主のサポートがより重要になります。定期健診でのチェックが欠かせません。
・ラブラドール・レトリーバー:遺伝性白内障の代表的な犬種で、血統により発症率が高いことが知られています。
・ゴールデン・レトリーバー:加齢性が多いですが、遺伝的要因で中年齢でも発症することがあります。
・シベリアン・ハスキー:特に遺伝性白内障が多く、若齢から進行しやすい傾向があります。
何歳から白内障に注意すべき?
白内障は加齢とともに増える病気ですが、犬種や体質によって発症の時期は異なります。年齢の目安を知ることで、早めにケアを始められます。
シニア期に多い発症パターン
一般的に白内障は7〜8歳を過ぎた頃から見られることが多く、シニア期に差しかかると発症率がぐっと上がります。加齢によって水晶体のたんぱく質が変化し、濁りが生じやすくなるのです。
特に小型犬は長寿な分、加齢性白内障が進行しやすい傾向があります。健康診断とあわせて目のチェックを受けると、早期対応が可能になります。
若齢で発症する場合もある
遺伝性の白内障は1〜3歳といった若齢で現れることもあり、シニア犬だけの病気ではありません。特定の犬種では早期から進行しやすく、視力を急速に失うケースも報告されています。
若いから安心と考えず、目の濁りや行動の変化に気づいたら早めに受診することが大切です。繁殖時の遺伝的要素も関わるため、飼い主が知識を持つことが予防につながります。
犬の白内障に関するよくある質問
(タップで回答)
白内障になった犬は普段の生活でどう支えればいいですか?
家具の配置を変えずに生活環境を一定に保つことで、視力が低下した犬も安心して過ごせます。散歩では段差や障害物に注意し、声かけでサポートすることが大切です。
(タップで回答)
白内障の犬に適した遊びはありますか?
視力が落ちても嗅覚や聴覚はしっかり働くため、音の鳴るおもちゃやにおいを頼りに遊べるゲームがおすすめです。安全に楽しめる工夫を取り入れれば、ストレス解消や運動不足防止につながります。
(タップで回答)
若い犬でも定期的に目の検診を受けた方がいいですか?
若齢犬でも遺伝性白内障が発症する場合があるため、年齢にかかわらず定期的な目のチェックは有効です。特に白内障になりやすい犬種では、1年に1度は眼科検診を受けるのがおすすめです。
(タップで回答)
白内障と診断されたら食事で気をつけることはありますか?
目の健康維持には抗酸化作用を持つ栄養素を含んだ食事が役立ちます。ブルーベリーや緑黄色野菜を取り入れたフードは、進行を遅らせるサポートになります。ただし与える際は量やバランスに注意が必要です。
白内障と向き合う飼い主のサポート
白内障は自然に治ることはなく、進行すれば愛犬の生活に大きな支障を与える病気です。しかし、飼い主が早めに変化に気づき、適切な対応を取ることで進行を遅らせたり快適な暮らしを支えることができます。
定期的な健康診断で目の状態をチェックし、必要に応じて点眼薬や手術を検討することも選択肢のひとつです。また、抗酸化成分を含む食事や、紫外線対策、肥満防止などの生活習慣の工夫も予防に役立ちます。
大切なのは「もう年だから」とあきらめず、愛犬に寄り添ったケアを続けることです。飼い主のサポートが、犬の残りの時間をより明るく安心したものにしてくれるでしょう。

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。
ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。
成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。
愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami
愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。
参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。
本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。