
犬のパテラ(膝蓋骨脱臼)で「グレード1」と診断されると、「いつか手術が必要?」「費用はいくらかかるの?」と不安になりますよね。
結論から言うと、グレード1は軽度の段階であり、日常のケアを徹底することで手術(片足20〜40万円)を回避し、一生を元気に過ごせるケースが多いです。
しかし、放置して環境が悪いままだとグレードが進行し、手術が必要になってしまうのも事実。
この記事では、愛犬の足を「一生守る」ために今すぐ飼い主ができる生活ケアと、万が一に備えた費用の知識を、愛犬家の目線でわかりやすく解説します。
パテラ(膝蓋骨脱臼)グレード1の状態と「手術の必要性」

パテラのグレード1は、膝のお皿が一時的に外れることはあっても、すぐに元の位置に戻る「軽度」の段階です。
この段階では、基本的に「メスを入れる手術」を急ぐ必要はありません。 痛みが出ることも少ないため、日常生活の中で膝への負担を減らす「保存療法」が治療のメインとなります。
指で押すと外れるが「自然に戻る」のがグレード1
グレード1は、獣医師が指で膝のお皿(膝蓋骨)を押すと外れますが、指を離せば自然に元の溝へと戻る状態を指します。
歩き方の特徴: 普段は普通に歩けますが、時折「後ろ足を一瞬スキップするように浮かす」といった、わずかな違和感が見られる程度です。
診断方法: 動物病院での触診がメインとなります。レントゲンではお皿の位置だけでなく、骨そのものの変形がないかを確認し、総合的に判断されます。
グレード2への進行を食い止められる「唯一の時期」
グレード1とグレード2の大きな違いは、「お皿が外れている時間の長さ」と「痛みの頻度」です。
グレード1: 外れても一瞬ですぐ戻る。痛みもほぼない。
グレード2: 外れている時間が長くなり、スキップの頻度が増える。痛みで足を着けないことが出てくる。
グレード1の最大の特徴は、飼い主さんのケア次第で「グレード2への進行を抑え、一生手術なしで過ごせる可能性が高い」ということです。いわば、愛犬の足を守るための「一番大切な準備期間」と言えます。
見逃し厳禁!パテラ「グレード1」の初期サイン

グレード1は軽度のため、歩き方の変化や痛みがはっきり出ないことも多く、飼い主の目では気づきにくい傾向があります。
ちょっとした違和感を見逃しやすい段階だからこそ、日常の動き方をていねいに観察し、小さなサインを早めに把握することが大切になります。
スキップ歩き・歩き方の違和感
グレード1で見られやすいのが、後ろ足を一瞬だけ浮かせる“スキップ”のような歩き方です。常に続くわけではなく、遊びの途中や歩き始めだけに出ることも多いため、飼い主が気づきづらい特徴があります。
短時間の違和感でも膝のお皿が外れかけているサインの可能性があるため、日頃の動きをよく観察することが大切です。
片足をかばう・座り方のクセ
軽度のパテラでは、痛みが目立たないものの、片足をそっとかばうように立つ姿勢や、横座りのように体を傾けて座るクセが出ることがあります。わずかな違和感の現れでも、膝のお皿が不安定な状態になっているサインかもしれません。
普段と少し違う座り方や、足を投げ出す姿勢が増えたと感じたら、早めに注意して様子を見ることが大切です。
なお、足の動きがおかしいように見えても、突然倒れてしまう、意識がぼんやりする、全身が震えるといった様子が見られる場合は、膝のトラブルではなく、てんかんなど神経の病気が関わっている可能性もあります。犬のてんかんの症状や受診の目安については、こちらの記事で詳しく解説しています。
➡ 犬のてんかん発作を徹底解説
悪化を防ぐために今すぐできる3つの家庭ケア
グレード1の悪化を防ぐために最も重要なのは、「膝への余計な衝撃をゼロにする」ことです。日々の暮らしの中で、飼い主だからこそ守ってあげられるポイントを3つに絞って解説します。
滑る床は「足腰の天敵」!滑り止め対策の徹底
室内飼いにおいて、最も膝に負担をかけるのが「フローリング」です。足が滑るたびに、膝のお皿を支える靭帯に無理な力がかかってしまいます。
具体的なアドバイス: 部屋全体に敷き詰めるのが難しい場合は、「愛犬がよく歩く動線」や「ジャンプして着地する場所」だけでも重点的にマットを敷くのが効果的です。
筆者の実感: 私の家でも、以前は一部だけマットを敷いていましたが、結局マットのない場所で滑ってしまうことがありました。滑り止め効果の高いタイルカーペットを「愛犬の通り道」に隙間なく敷き詰めてからは、格段に足取りが安定したと感じています。
現在、楽天とAmazonのみ取り扱いがあります。ヤフーショッピングは取り扱いがないため、サイトの中でいちばん人気のサポーターをご紹介しています。
滑り止めとして役立つ肉球パットの使用もおすすめです。
膝への負担を物理的に減らす「唯一の方法」は体重管理
意外と見落としがちなのが体重管理です。体重がわずか数百グラム増えるだけでも、細い脚の関節にかかる負担は数倍に膨れ上がります。
具体的なアドバイス: グレード1と言われたら、まずは「適正体重の下限」を目指すくらいの意識がちょうど良いです。
フードの活用: 単におやつを減らすだけでなく、「関節サポート成分」と「低カロリー」が両立されたフードへ切り替えるのが近道です。これは、膝への物理的な負荷を軽減できる唯一の方法と言っても過言ではありません。
散歩を工夫して「天然のサポーター(筋肉)」を維持する
「膝が悪いから安静に」と考えがちですが、動かないと筋肉が落ち、逆に関節が不安定になります。
具体的なアドバイス: 激しい運動やジャンプ、急旋回は避けるべきですが、平坦な道をゆっくり歩く散歩は続けましょう。1回の時間を短くして、回数を増やすなどの工夫がおすすめです。
筋肉の役割: 膝周りの筋肉を維持することは、いわば「自前のサポーター」をつけているのと同じ状態です。無理のない範囲で歩く習慣を大切にしましょう。
日常の食事から膝への負担を減らしたい場合は、関節ケアに配慮した総合栄養食を選ぶとより安心です。パテラや関節トラブルが気になる子に向くフードについては、下記の記事で具体的な銘柄と選び方を紹介しています。
➡ 犬の関節サポートにおすすめのドッグフード3選|膝蓋骨脱臼・関節炎ケアにも
パテラ悪化を防ぐ!おすすめケアフード3選
毎日の食事で適正体重を保ち、関節をサポートすることは、パテラ悪化を防ぐための大きな鍵となります。ここでは、愛犬の膝への負担を減らすためにおすすめのドッグフードを3つ厳選してご紹介します。
体重管理と食いつき重視なら「うまか」

関節サポート成分(グルコサミン・コンドロイチン)が配合されつつ、脂質控えめで体重管理がしやすいのが大きな魅力です。
お出汁のようなカツオの香りが広がり、食いつきで悩む愛犬にもぴったりです。毎日の予防や、グレード1の軽度ケアを美味しく続けたい方に選ばれています。
筋肉維持と炎症対策には「モグワン」
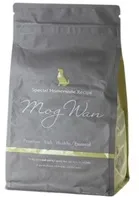
グレインフリーで消化に優れ、サーモン由来のオメガ3脂肪酸が豊富に含まれているドッグフードです。
良質な高タンパク設計のため、膝を支える太ももの筋肉維持をしっかりサポートしてくれます。関節専用ではありませんが、パテラ予防として多くの小型犬の飼い主さんから選ばれています。
本格的な関節ケアなら和漢未来のフード

「これ以上絶対に進行させたくない」という、本気で関節ケアに取り組みたい方におすすめのドッグフードです。
栄養学に基づいた和漢植物が配合されており、愛犬の骨と関節の健康を根本から見つめ直すことができます。より本格的で頼もしいサポートをお求めの飼い主さんにぴったりです。
グレード1の検診費と進行した場合の手術費用の相場

パテラと診断されると、まず頭をよぎるのが「お金」のことではないでしょうか。グレード1の段階では高額な費用がかかることは稀ですが、進行した場合にはまとまった出費が必要になります。
将来の大きな負担を避けるためにも、今の段階でかかる費用と、将来のリスクを比較して把握しておきましょう。
【今かかる費用】定期検診と保存療法の目安
グレード1の場合、基本的には「保存療法(手術をしない治療)」となります。この段階で必要になる主な費用は、以下の通りです。
定期検診代: 約3,000円〜10,000円(診察料+必要に応じた触診・レントゲン)
サプリメント代: 月々2,000円〜5,000円程度(関節をサポートする成分など)
環境改善費: 数千円〜(滑り止めマットやステップの購入など)
グレード1であれば、通院頻度も数ヶ月に一度の経過観察で済むことが多く、家計への負担も比較的抑えられます。
【将来かかる費用】グレード進行時の手術・入院費の相場
もし生活環境の改善を行わず、グレード2、3へと進行してしまい、外科手術が必要になった場合は、以下のような高額な費用が発生します。
手術・入院費: 片足 20万円〜40万円
術後のリハビリ・通院費: 数万円〜
パテラの手術は、骨を削ったり靭帯を調整したりする高度な外科処置が含まれるため、入院期間も含めると非常に大きな出費となります。両足同時に手術が必要になった場合は、さらにその倍近い費用がかかるケースも珍しくありません。
💡 編集部minamiのアドバイス
「うちの子はまだグレード1だから大丈夫」と油断してフローリングのまま生活させていると、ある日突然キャン!と鳴いてグレードが進んでしまうことがあります。
数十万円の手術費を払うことになる前に、数千円の滑り止めマットを敷いてあげること。 これが、愛犬の体にとっても、飼い主さんの財布にとっても、最も優しい選択だと私は考えています。
| グレード1(今) | グレード進行後(将来 | |
|---|---|---|
| 主な対策 |
定期検診 |
外科手術・入院 |
| 費用の目安 | 数千円~ | 20万円〜40万円 |
| 愛犬の負担 | ほぼなし |
全身麻酔 |
パテラになりやすい犬種と注意点

パテラは体格や骨格の特徴によって発生しやすい犬種があり、遺伝的な要因が関係することもあります。普段の生活環境によって負担が大きくなる場合もあるため、注意点を知っておくと安心です。
小型犬に多い理由と気をつけたい体の特徴
パテラは小型犬に多く見られる傾向があり、特に膝周りの骨が細い犬種は負担がかかりやすいとされています。ジャンプや段差の上り下りが多い生活をしていると膝に衝撃が加わりやすいため、日頃の動き方にも注意が必要です。
筋力がまだ十分でない成長期の子犬や、体重が急に増えたときも関節への負担が大きくなるため、生活環境を整える意識が大切になります。
代表的な犬種と日常での予防ポイント
パテラになりやすいとされる犬種には、チワワ、トイプードル、ポメラニアン、ヨークシャーテリアなどが挙げられます。これらの犬種は膝が外れやすい骨格を持つケースも多く、滑りやすい床や急な段差がある環境では症状が出やすくなることがあります。
普段から走るスペースを整えたり、ジャンプを減らす工夫を取り入れることで、膝への負担を少しずつ軽くしていくことができます。
・チワワ
体が小さく骨が細いため、膝関節が不安定になりやすい傾向があります。体格に比べて運動量が多い子も多く、その分膝への負担がかかりやすい犬種です。
・トイプードル
後ろ足が細長く、関節にかかる力のバランスが崩れやすい体のつくりをしています。活発でジャンプを好む性格も、膝蓋骨脱臼の発症リスクを高める要因となります。
・ポメラニアン
小型で骨が華奢なうえ、よく動き回る活発な性格から膝に負担がかかりやすいです。成長期に骨格がしっかりと形成されにくい子もおり、注意が必要です。
・ヨークシャーテリア
脚が細い小型犬であるため、膝のお皿がずれやすい傾向があります。遺伝的な要素が関係しているといわれることもあります。
・パピヨン
活発でジャンプが好きな性格に加え、後ろ足が細いため膝関節への負担がかかりやすいです。その結果、関節へのストレスが蓄積しやすいとされています。
・ジャックラッセルテリア
小型で関節が華奢なうえ、ジャンプや激しい運動を好むため、膝に大きな負担がかかりやすい犬種です。そのため、膝蓋骨脱臼を起こしやすい傾向があります。
・シェットランドシープドッグ
中型犬の中では骨格がやや華奢で、膝関節に負担がかかりやすい体質です。運動量が多く活発に走り回ることが多いため、繰り返しの衝撃によって膝蓋骨脱臼を発症するリスクが高いといわれています。
パテラ(膝蓋骨脱臼)の悩み・疑問Q&A
パテラについてよく寄せられる疑問や不安にお答えします。症状の見極め方や治療に関する判断など、飼い主さんが気になるポイントをQ&A形式でまとめました。
(タップで回答)
グレード1でも手術は必要?自然に治る?
グレード1では保存療法が基本で、まずは生活環境の工夫や体重管理で様子を見ることが多い段階です。自然に完治するというより、悪化を防ぎながら安定した状態を保つことが大切とされています。手術が必要かどうかは、症状の変化を見て動物病院で判断してもらうと安心です。
(タップで回答)
パテラは両足に起こることもありますか?
はい。膝蓋骨脱臼は片足だけでなく、両足に発症することもあります。特に遺伝的な要因や骨格の癖がある場合は、反対側の足にも注意が必要です。
(タップで回答)
パテラの犬に自宅でできるケアは?
滑りにくいマットの設置や体重管理、適度な運動、ジャンプを避ける生活環境づくりなどが有効です。太ももの筋肉を育てることで関節の安定性も高まります。
(タップで回答)
すぐに病院に連れていくべき症状は?
急に足を上げたまま動かない、歩き方に強い違和感がある、触ると痛がるといった症状がある場合は、早めに動物病院を受診しましょう。進行性の病気の可能性もあるため、放置は禁物です。
(タップで回答)
成犬や子犬のパテラは自然治癒する?
自然に完全に治るというより、生活の工夫で安定した状態を保つことが大切とされています。成長期の子犬は筋力がまだ十分でないため負担がかかりやすく、成犬でも体重や環境で症状が変わることがあります。日々のケアを積み重ねることで悪化を防ぎやすくなります。
(タップで回答)
パテラの手術費用はどれくらい?
片足の手術費用は一般的に20万〜40万円が相場です(入院費込み)。両足やグレードが重い場合はさらに高額になることもあります。術後の再診やリハビリ費用も考慮して、トータルでの見積もりをしておくことが大切です。
愛犬の足を守るために|知っておきたいことまとめ
膝蓋骨脱臼(パテラ)は小型犬に多く見られる関節トラブルのひとつですが、グレード1のような軽度の段階であれば、日常の工夫で負担を和らげながら安定した状態を保っていくことができます。
滑りにくい環境づくりや体の使い方の見直し、体重管理につながる食事の調整など、暮らしの中で取り入れやすいケアが多いのも特徴と言えるでしょう。
気になる歩き方や座り方のクセが続くときは、早めに状態をチェックしておくと安心です。無理をさせず、できる範囲のサポートを積み重ねることで、愛犬が心地よく過ごせる毎日に近づきます。
正しい知識を味方にしながら、これからも健やかな足をやさしく見守っていきましょう。
トップページ

こんにちは、愛犬ごはんノート編集部 minamiです。現在は柴犬のムギ(9歳)とザネ(7歳)と暮らしています。
ムギは子犬の頃から皮膚が弱くアレルギー性皮膚炎があり、ザネは内臓が少し繊細。日々の食事が体調に大きく影響するので、これまで20種類以上のドッグフードを試してきました。
成分や原材料について調べるのが趣味のようになり、自分なりに学んだことや、実際に愛犬に与えてきたフードの体験談をこのサイトでご紹介しています。
愛犬の健康に不安がある方や、どのフードを選べばいいか悩んでいる方にとって、少しでもヒントになればうれしいです。
運営者名:愛犬ごはんノート編集部 minami
愛犬の食事管理歴15年以上、20種以上のフード比較経験。
参照・取材方針:公的機関・学術資料を一次情報として優先し、体験談とは区別して解説します。
本記事は一般的情報であり、診断・治療の代替ではありません。医療判断は獣医師へ。




